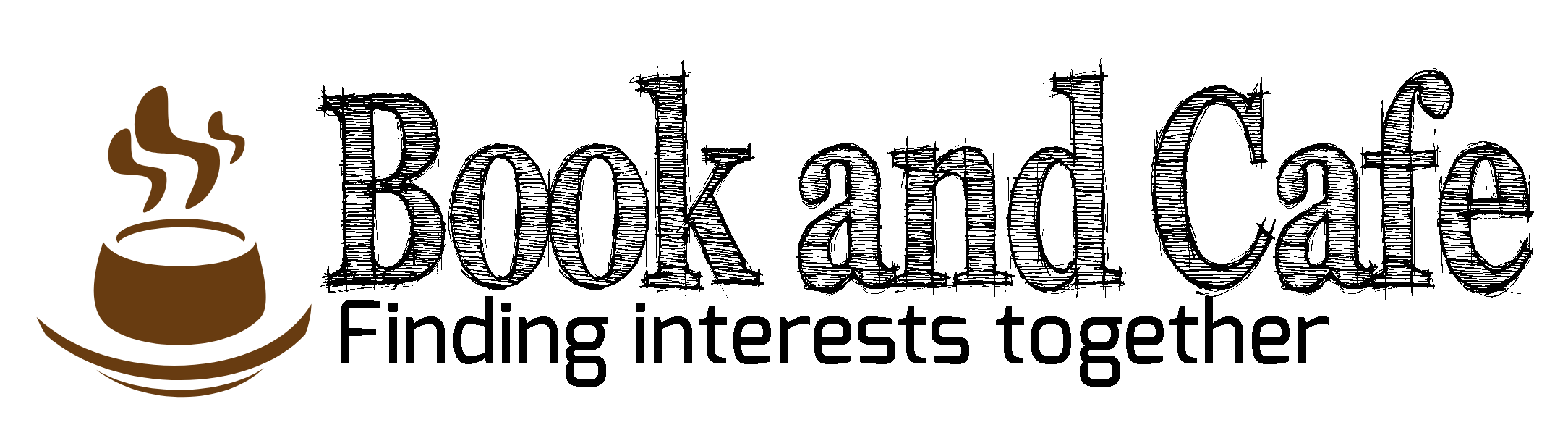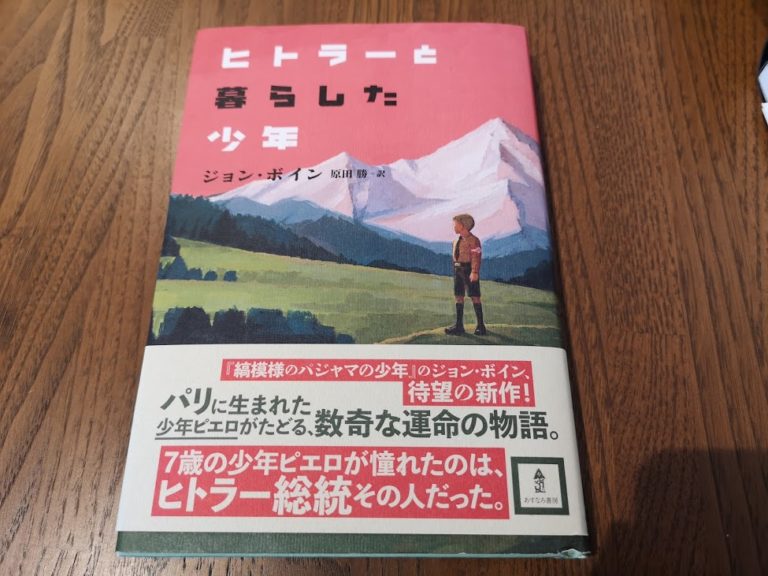あらすじ(なるべく本筋に触れないよう)

ドイツ人の父とフランス人の母のもとパリで生まれたピエロ。同じくらいの子供の中でも小さく、性格も大人しかったため、目立つようなことはなかった。それでも、友人アンシェルと飼い犬ダルタニャンに囲まれ、その時代どこにでもみかける少しまずしい少年として育つはずだった。
しかし、度重なる家庭不幸をきっかけにオルレアンの孤児院へと引き取られ、その後、ドイツ・ベルクホーフのとあるお屋敷でメイドとして勤務していた叔母からの連絡を受け、引き取られることとなる。
その屋敷は、当時飛ぶ鳥を落とす勢いでドイツの権力を集めていたヒトラーの別荘だった。そんな時代の中心地で、世間がどういう状況だったかなんて何も知らないピエロはヒトラーとの交流を深めていくこととなる。
本書には、そんな不遇ながらも、心優しかったピエロが、ヒトラーと周りの大人たちからの影響を受け、子供から少年、そして青年へと育っていく様子が克明に描かれている。 何も知らなかった少年は何かを知る立場へ。そのとき、ピエロはどう動くのか。
この本は戦争と権力のなかでいかに人間が弱いか、それをまざまざと教えてくれる作品です。
感想(ネタバレも・・)
内向的も優しい幼少期
小説は第二次大戦の足音が忍び寄る1936年、ピエロが7歳のころから始まります。場所は第一次大戦(1914-18)の傷跡や経済的な不況に苦しむパリです。
ピエロの両親は健在でしたが、ドイツ軍の兵士として戦争に参加した父の精神的な後遺症、そんな父とフランス人の母のあいだでたまに起こる祖国に関するけんか。ピエロは無邪気にフランス語とドイツ語を操るようになりますが、パリのコミュニティでの立ち回りは難しかったんでしょう。事実、背も低く、積極的な立ち回りをしないピエロがいじめられていた描写もあります。そんな、ピエロの支えとなったのが、近所に住むユダヤ人で耳が聞こえないアンシェルと飼い犬ダルタニャン。耳が聞こえないアンシェルと意思疎通するために手話を学んだピエロ。ただ、そんな交流の中にも周りからはユダヤ人への蔑視の言動が垣間見られます。
その後、ピエロの周辺に降り注ぐ不幸の結果、そして引き取り手が近隣におらず、連絡もままならなかったため、ピエロはオルレアンの孤児院へと引き取られることとなるのですが、ここでも同様に孤児院コミュニティに馴染めず、いじめを受けることに。いじめを先導するユダヤ人ユゴーと、そんなピペロを擁護する賢く優しいジョゼット。淡い恋心に似たようなものをピエロはジョゼットに抱き、社会的な適応をしていきます。ただ、そんな賢いジョゼットも自然とユダヤ人に対する差別発言をして、その時代の陰鬱さが垣間見られることとなります。
舞台はベルクホーフへ
この本では一貫してナチ関係者は悪として描かれています。駅舎でピエロの足を踏んで手を助けなかったり、電車の中では弱者から食べ物を取り上げたりしています。
そして、その過程でピエロはヒトラー・ユーゲント(ヒトラー青少年団)の権力に何とも言えない感情を抱くこととなります。ピエロにとって嫌悪の対象のはずなのに、制服を着た少年たちに畏怖を感じてしまう。そんな複雑な感情を抱くことに。
過去との決別

By Bundesarchiv, B 145 Bild-F051673-0059 / CC-BY-SA, CC BY-SA 3.0 de, Link
おばさんのベアトリクスはピエロに対していくつかの教育をします。今後はフランス語を使わず、フランスと母のことも忘れること。また、ベアトリクスは母が買い与えた服を焼き払い、そしてペーターというドイツ語読みの名前を使うよう命令します。そしてヒトラー式敬礼を教え込みます。
その後、ピエロはヒトラーと出会い、何とか間違いを犯さず敬礼を行うとその後ヒトラーはピエロのことを悪い扱いをしません。ただ、特別待遇というわけではなく、下僕、もしくはペットのように扱います。ヒトラーが以前に自身が飼っていたペットを思い出しながら、また、現在飼っているペットを思いながら。
ヒトラーとピエロの破滅
そんなピエロも成長するごとに、周りの状況を少しずつ理解していきます。ヒトラーに対する周りの畏怖を肌で感じ、彼の別荘に住む自分に対する特別感。また、ヒトラー・ユーゲントと同じ制服を着るようになるとさらに自尊心が満たされていきます。それに伴い、周りにも彼のことをきちんと遇することを求めていきます。さらに以前はベアトリクスから強制されていた数々のことを自ら率先して行い、またアンシェルとの文通を拒絶するようになります。
そんなぺエロに対して良心を発揮するベアトリクスをはじめ、屋敷の使用人たち。幾重にわたってぺエロが道を踏み外さないように、そして自身の国が間違った方向に進まないよう、自身のできることを考えます。しかし、それらに少しばかり気を咎めながらもヒトラーに気に入られようと、そして周りにいる要人たちに近づこうと振り切りってしまいます。
叔母のベアトリクスと運転手エルンスト、そして厨房のエマ、麓の文房具屋カタリーナをも裏切ってしまい、最後、彼の周りにはだれも残りませんでした。
彼の一生はまるでヒトラーのそれなのかもしれません。弱者だった幼少期から何とか抜け出そうとして、必死に自分の居場所を作っていった。その過程で周りを排除していつの間にか周りから人がいなくなっていったという。
現実のヒトラーは自殺を遂げますが、エピローグでのピエロの過去を巡る旅には何とも言えない気持ちにさせられました。そして、最終ページ、どんな残酷な状況にあっても希望を垣間見せてくれる筆者には感謝をしたいな、なんて思いました。
結局、 常にどこかに居心地の悪さを感じつつも、 ピエロは周りの環境や無知を理由に権力に傾倒していきました。そうなってはいけないと誰もがわかることですが、戦争や権威の前では普通の人間だったら誰しも飲み込まれてしまうのかもしれません。だからこそ、そうならないよう、色んなことを教えてくれるのが、この本だとおもいます。
次の一冊
ジョン・ボインの代表作『縞模様のパジャマの少年』は間違いなく、次の一冊としてお勧めです。これも戦争における理不尽さを訴えていて本書を興味深く読んだ方なら、間違いなく楽しめるはず。
また、著者のジョン・ボイン氏はyoutube上で作品紹介やインタビューにも応じているので興味ある方はご覧になってみてください。下のサイト以外にも”John Boyne Interview”で多数でてきます。
雑な閑話休題

ピエロはなぜペーターというふうに呼ばれるの?
本筋とは関係ないのですが、本作の主人公の名前’ピエロ’といいます。そして、後にドイツ語呼びのペーターと呼ばれるようになります。じゃ、フランス語読みってペターとかじゃないのって思ったし、ピエロだったら別のドイツ語読みがあるのでは、って思ってサイトを探したら、苗字に関する解説があったのでここに紹介を(リンク)。
ピエロという苗字は中世のブルターニュ地方でピエールの派生として使われるようになり、もともとは岩を意味するペトロやピーターとして使われていたとのこと。そのため、この本ではピエロをそのままドイツ語読みしてフランスにルーツがあるとばれるよりは、ドイツでも一般的でピエロとも親和性のあるペーターとして呼ぶようになったのかな、なんて思いました(個人の考察であり、少し自信がありませんが・・・どなたか真実をご存知の方はご指摘くださいませ)。
この本をいつまでも心に留める絶妙な『あとがき』
この本を最終章、エピローグと読み進め、作者の謝辞等を読み終えると現れるのが訳者のあとがきです。このあとがきがとても良かったんです。まず、本書を振り返りつつ、他のジョン・ボインのテーマや特徴に触れつつ、本書のそれを指摘。そして読者に考えてほしいことを訴えています。
最後にジョン・ボインの他の作品を紹介し、次の書へと誘います。その締めくくり方がなんとも絶妙で、読後の熱量を維持させながらも次への本への渇望を刺激してくれるんです。・・・わたしもまんまとネットで本を注文してしまっていました。。わたしもそんな筆者のような紹介文や感想文をいつか書けるといいな、とも思いました。精進していきたいと思います、、、