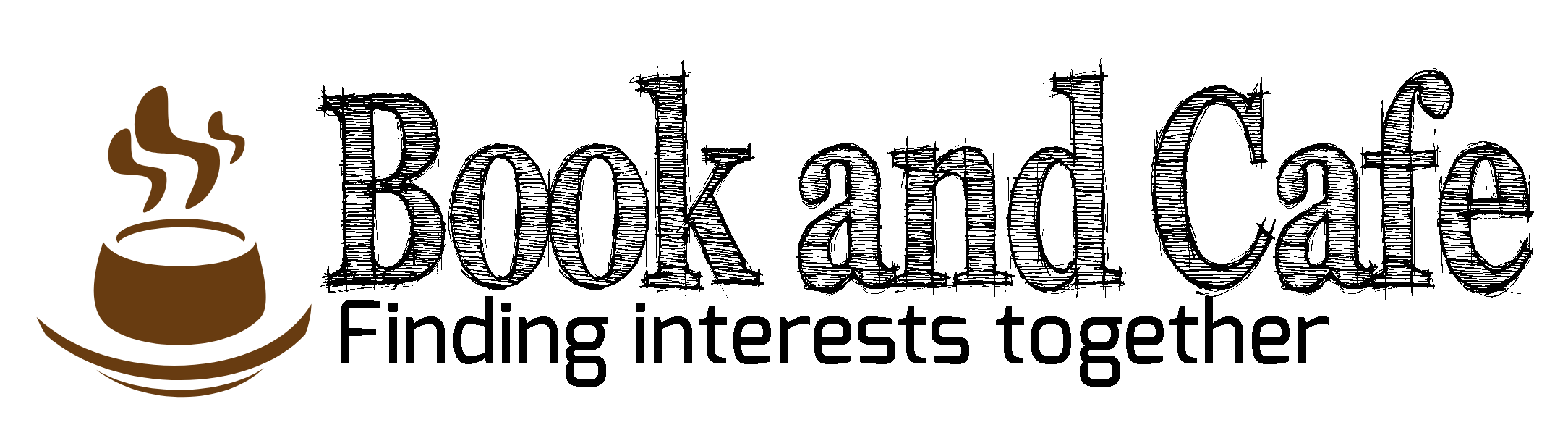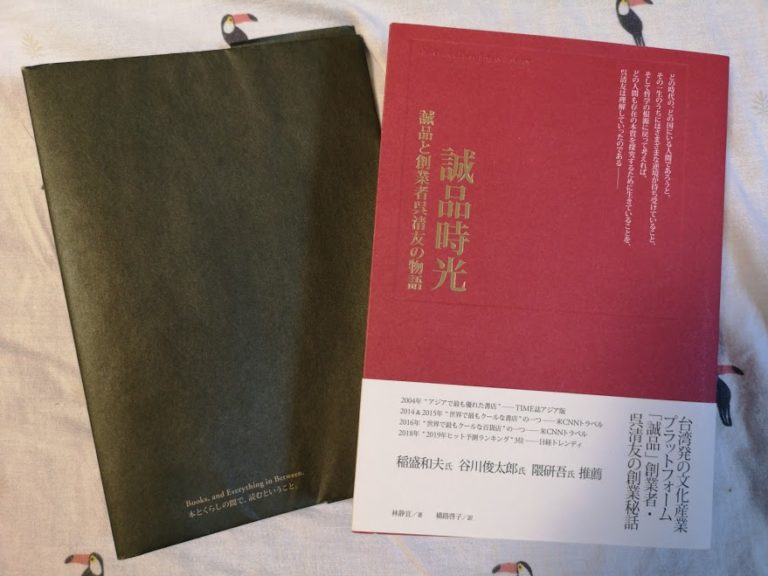内容

この本は台湾で大成功し、2019年9月27日に東京日本橋に進出した総合小売グループ『誠品』とその創業者である呉清友氏を追ったものです。彼がどのような境遇で生まれ、何を精神的な支柱としてきたのか。そしていつ既存のビジネスとは全く違う誠品というブランドを創りあげることになったかが書かれています。
必ずしも恵まれた環境で生まれたとは言い難い呉氏。それでも絶え間ない努力と向上心をもって若くして厨房器具の会社を買い取り、業界トップへと成長させます。
その後、自分の進むべき道が書店を中心とする文化発信にあると強く感じるようになります。それが誠品へと繋がっていくのです。ただ、現在の華々しい誠品の売り場からは想像ができないほどその道のりは困難で険しいものでした。
この本では創業者の呉清友氏を物語の中心に置きながら、時に社員から、時には家族や後継者の視点を添えています。章を追う毎に関係者視点は増え、誠品を多角的にとらえられるようになります。その様子は、まるで呉清友氏の分身ともいえる誠品が、多くの人に関わっていく中でみんなの誠品になっていく様でした。
では、単なる伝記なのかというとそうではありません。彼と誠品が育った時期は台湾をはじめとする中華圏の変貌の時期でその様子もつぶさに知ることができます。ある意味、台湾文化を熱かった叙事詩的な作品なのかもしれません。
さらにこの本は誠品の展開する売り場に込められたコンセプトが伝わってきます。そのことによって、日本橋の売り場はもちろん、台湾や香港、蘇州、深圳の売り場にも足を延ばしたくなる、そんな旅行本かもしれません。
日本橋に誠品ができてぐっと身近な存在になった今、この本で誠品の神髄に触れてみてはいかがでしょうか。
*amazonでの取り扱いがありませんせんでしたので商品リンクはありません(本の装幀は写真の通りです)。誠品の通販サイトは現状日本向けではないのでこちらもリンクは付けていません。申し訳ないです。日本橋を訪れた際に本書を手に取ってみてください。
振り返りながら感想
原点ともいえる出来事

物語はこんな風に始まります。
呉清友氏(Wu Qingyou, Robert Wu)がイギリスを訪れギャラリーオーナーと交流を深めた帰り、ハワイに立ち寄ることに。そこで立ち寄ったアパレルショップに裁縫商の兄からもらったハーフパンツと同じものをみつけた。驚いたことに、卸値の10倍の値段がつけられて販売されていたという。彼はその時に自分の役割を認識したといいます。それは台湾をはじめとする中華圏のブランドを育てて発信することでした。
その時すでに彼は「誠建(厨房設備の販売会社)」 の社長として成功を収めていました。そのビジネスを伸ばしていく、もしくは売却すれば間違いなく順風満帆な生活をおくれたことでしょう。
でも、呉清友氏は事業が順調な時も、「なぜ自分が成功しているのか」、「なぜ自分なのか」と常に心で問うてたといいます。その答えを求めて彼は多くの本を読み漁りました。その中でも特に、シュヴァイツァー、弘一大師、ヘルマン・ヘッセの考え方や人生観には影響をうけたそう。そして、上述のイギリスでのギャラリーでの体験とハワイでの経験が大きなきっかけとなり、「文化とアートの書店」を作ろうと決意します。
台湾の有名書店で働いていた人をヘッドハンティングし、会社内に新規ビジネスの準備室を立ち上げ、いよいよビジネスを始めようとしたときに呉氏は病に倒れます。生死の境をさまよいつつも、彼の今まで培った人脈、家族の献身的な支えの結果、現場に復帰することとなります。

この出来事はいよいよ彼に誠品のビジネスが天命だと思わせるようになります。そして翌1989年3月、誠品第一号店を台北市の中心街である仁愛路ロータリーの一角にオープンします。
この冒頭部分だけでも非常に面白く、本に引き込まれるような展開でした。こういう一代記が好きな方は、日本橋の誠品書店でこの本を購入してみてください。下の感想はあまり気にしなくて大丈夫です。たぶん、この後の展開もお好み内容になっているはずです。
誠品の考え方

本書によれば、80年代末の台湾の書店は必ずしも洗練されていませんでした。本は地面に置くし、それを積み上げたりもするのが一般的だったよう。一方で、誠品は「本をもてなし、人をもてなし、心をもてなす」というコンセプトで他の書店とは一線を画したものとなりました。
誠品の建築、芸術、文学を中心としたラインナップの本棚はとても優雅で、お店の中には、そのほかにも花屋やティーハウス、欧米の工芸品等も扱っていました。今では珍しくないですが、誠品は様々な書店を取り扱った複合的な書店としてオープンします。
その誠品書店のオープン2か月後には誠品画廊もオープンし、その気品あふれるスペースは地元で大いに話題となったそう。誠品は店舗網を拡大していく中で、文化芸術の専門店から、「ヒューマニティー、アート、クリエイティブ、ライフ」をコア・バリューとした総合書店へと変化していきました。また、読書を中心にしつつ、「本と暮らしの間」にある複合的なイノベーションに力を注ぎ、様々な事業を展開するようになります。
誠品という名前について

色んな名前を検討して行き着いた誠品という名前。そこには呉清友氏の親との関係があった。彼の親は缶詰工場の工場長となり、ある程度暮らしは裕福でした。そして非常に実直でとある連帯保証がきっかけとなり、破産します。その後、ゼロから再び養殖業などを起こしていくのだが、その際に親から言われた言葉が、「富はいつか無になるが、『誠』という字は生涯尽きることのないものだ」という言葉。これを以て呉氏は事業の一字目にしました。そして続く言葉として選んだのが「品」。これは文化事業に必要なセンス、仕事に必要な品質、人間の人格に通じるものだという。
そして、店名eslite。実は英語のelite(エリート)が商標登録されていたため、フランス語の「 éslite」という言葉を用いたそう。これには階級という意味ではなく、人が持つ人それぞれの潜在力を発揮するという想いを込めているといいます。
だから、誠品の展示には品格があって客に向き合った誠実さを感じられるのかもしれません。とにかく、そんな想いが店名に込められているそうです。
誠品の躍進
もう少しだけ本を振り返ってみます。
.jpg)
1990年代の台湾は変革期だったといいます。戒厳令が解除され、90年代半ばには出版・言論の規制が解除され、自由な雰囲気が成長しました。そして、「大胆な新しさ」と「古典的な古さ」を多様な文化が育まれました。この二つを兼ね備えた場所、それが誠品でした。
1992年には台湾ビジネスの中心地に出店すると「読書企業文化」をテーマとして企業人の読書振興にも取り掛かります。周りからはビジネス書しか売れないといわれていたこの店舗でも、誠品がイベントや特集等で開拓を続けた結果、今では文芸書がよく売れるようになったといいます。1993年には中部の自然科学博物館内に「自然生態読書」をテーマに書店をオープン。書店毎のテーマを決めて続々とオープンしてきます。さらに、1999年には誠品書店敦南店が世界初の「眠らない書店」として24時間営業を始めます。
90年代、店舗網を拡大する誠品は一見順調に見えますが、この裏で赤字を抱え続け、その期間は15年にも及んだそうです。
本書の中で、呉清友氏はこの時の心境を非常に複雑な思いで振り返っています。そして、自身の経営に対しては辛口の評価を下しています。それでも事業を続けることができたのは彼や彼の周りの支援者がいたからです。例えばASUSの創業者 童子賢氏 がそうだったとのこと。支援者たちは赤字にも拘らず、増資の要請に快く答えたそう。呉清友氏の経営センスと誠品のフロアが絶対に台湾のためになると確信し、応じたそうです。
ちなみに誠品の個性的な書店作りは、他社からの差別化の結果ではないと呉清友氏は言います。唯一無二の座標にある各書店には、その空間でしかできないものがある。結果として誠品の各店舗のようなユニークな店舗ができると、本書の中で詳しく語っていました。
もちろん、誠品もただ赤字をたれがなしていたわけではありません。経営の効率化についても推し進めます。90年代後半からは多角化が進んだビジネスに対してERP(基幹業務システム)を導入しはじめ、2001年には物流センターを創設しています。一方で店舗の合理化も進めています。
そして、2004年とうとう赤字を脱却するに至ります。ただ、この赤字の時期に投資したものは決して無駄ではありませんでした。当時業界に先んじて導入した物流センターやERP等のノウハウは中国でも展開し、他社に対しても物流センター導入や更新時のコンサルティング等を行うようになり、幅広い先端ノウハウをもった企業としてもみられるようになりました。
次代に受け継がれる誠品の精神
現在、誠品グループは呉清友氏の息女、呉旻潔(Min-Chieh Wu ,Mercy Wu )氏によって率いられています。彼女のキャリアはもともと誠品にはありませんでした。海外の大学を卒業した後、海外通信社に身を置き、その後に偶然とも必然ともいえないエピソードの中、誠品に入社します。そんな彼女は会社でも家でも呉清友氏のことを父といわず、会長と役職名で呼んだそう。それくらいに公私を分けて仕事に取り組んだそう。
そんな彼女は幼少期から赤字だった誠品を知っていたので入社したその期(2004年)に黒字転換したことがにわかには信じがたかったといいます。そして、事実その黒字収益の内訳は脆弱なものでした。一店舗に頼った収益、浮き沈みの激しい画廊事業に依存したりと、本業が盤石とはいえない状況が続きました。
そこで彼女は誠品の売り場での問題点等を洗い出す作業に取り掛かります。実は呉清友氏が長年経営を行った結果、現場ではセクショナリズムが進んでいました。誠品の顔ともいう書店部門は数字を用いなくなり、一方で誠品の収益を支えていた販売部門はそんな書店部門に対して悪い印象を持っていました。また、とある時期に企画したイベントでは、同一人物に対して二部門がアプローチして競合したことさえあったといいます。そんなバカげた状況を見て、人事交流だったり、コミュニケーションが必然的にできるようなシステムを導入するなど、様々な施策を実施して一体感を取り戻したのです。
彼女曰く、黒字転換できたこの時だからこそ、スムーズな改革を行うことができたと。黒字収益を原資として使い、売り場改革や人事制度改革を行い、誠品をさらに飛躍できるようにします。また、過去に取り組んだことのない事業にも参画してさらに事業領域を広げていく。そんな彼女をみて、呉清友氏は第一線から退き、自分は未来への種まきを再び始めました。ホテル業や不動産業です。誠品が提案するライフスタイルを恒常的に提供できる地を人々に提案する、そういう事業に取り組んでいきます。 2013年には安定的かつ永続的な事業を遂行するために誠品は台湾市場に上場しました。さらなるファンを増やし、またさらなる飛躍のため、今日も誠品は人々と読書を結び付けています。
2017年、呉清友氏は惜しまれつつ、この世を去りました。それでも彼の意志は誠品と共に次代に受け継がれている気が、この本を読んで思いました。
5つのメッセージ

本書には5つのメッセージが収められています。呉清友氏からの従業員向けメッセージだったり、 呉旻潔氏からの父親にあてた手紙だったりと。どれも真心のこもったメッセージであり、受け取った側はこの人物だったり、事業に携われたことを誇りに思うような内容になっていて、間接的に本書に厚みを与えています。
そして、特筆すべきなのが最後に書かれた手紙です。それは呉清友氏が息子あてに書いたものでした。
この本のどこにも彼のご子息に関する記述はありませんでした。そしてその理由や誠品の事業に対してどこまでも真摯にあろうとする姿が、この手紙を読んでわかるような気がします。それは告解のような文章でもありました。もちろん、彼には社会に奉仕するという信念もあったでしょうけど、それ以上に多くのことが含まれていた気がします。ぜひ読んでほしいと思う文章でした。
本について
本の概要
- タイトル:誠品時光-誠品と創業者呉清友の物語-
- 著者:林静宣
- 訳者:横路啓子(よこじ けいこ)
- 発行・装幀:誠品股份公司
- 印刷:立屹彩藝印刷有限公司
- 第1刷 :2019年9月
- ISBN978-957-8599-89-8
- 備考:台幣450元(販売価格2700円+税)台湾からの輸入書
関係サイト
- 誠品生活: https://www.eslitecorp.com/
- twitter: @eslite_japan
著者関連のSNSは調べた限りありませんでした。ただし、台湾語が分からないので、もしかしたらあるかもしれません(ご存知の方いらしたら、教えてください)。誠品については語学の壁に当たることが結構ありました。台湾市場に上場しているのでHP上にはアニュレポやコーポレートレポート等の情報があるのにどれも読めず。。。もちろんグーグル翻訳はあるのですが、正しいのか微妙なんですよね。
上の誠品のサイトは日本からつなげば日本語のページに飛ぶようになっていますのでぜひチェックしてみてください。日本では展開していない他の事業も知ることができますし、本書で紹介された台湾や中国の書店の雰囲気が少なからずわかります。もちろん、その中にはCNNが2016年に選んだ“世界で最もクールなデパート14選(記事リンク)”の誠品生活松菸店ややはりCNNが2015年に選んだ“世界で最もクールな書店18選(記事リンク)”の誠品敦南店(リンクは特設サイト)も確認することができます。
次の一冊
この本を読んでいると台湾の書店やその仕組みについてもっと知りたくなる人もいるでしょう。もしくは中国や香港のそれについて学びたい人もいるかも。とりあえず今回は以下の本をご紹介しておきます。

本の未来を探す旅 台北 [単行本(ソフトカバー)]内沼晋太郎朝日出版社2018-12-12
この本の著者で編集もされている内沼さんは下北沢にある『本屋B&B』の創業者の一人でもあります。この本は台湾のインディペンデントな本屋を中心に描いていますが、誠品書店についても書かれています。機会があれば店頭でチェックしてみてください。
雑な閑話休題(雑感)

この本を読むと蔦屋書店やTSUTAYA BOOKSを展開するTSUTAYA(CCC)や無印ブランドを展開する良品計画との共通点や相違点がよくわかります。また、影響を受けたかもわかります。
いずれの会社もライフスタイルを提案すべく、中核事業は異なりますが、幅広い商品ラインナップを揃えているのは共通しています。そして、いずれの会社も比重に差はあれど本を扱う部門を持っているということ。それは面白い共通項ですね。
また、今回この誠品の様々な事業部門やお店の様子を知るにつれ、非常に似た組織を思い出しました。それはNYPL、ニューヨーク公共図書館です。この二つは目的も組織体も異なりますが、結果として非常に似たような機能を持っている気がします。市民を豊かにさせる、書棚、コンテンポラリー・アートのギャラリー、演劇や演奏を行うことのできる舞台、ビジネスサポート等々。
そしてその目標も似ています。地域に根差し、地域住民の導き・支える存在となる。そんな組織はいつの時代でもどこの地域でも求められているんだなと本書を読みながら思いました。