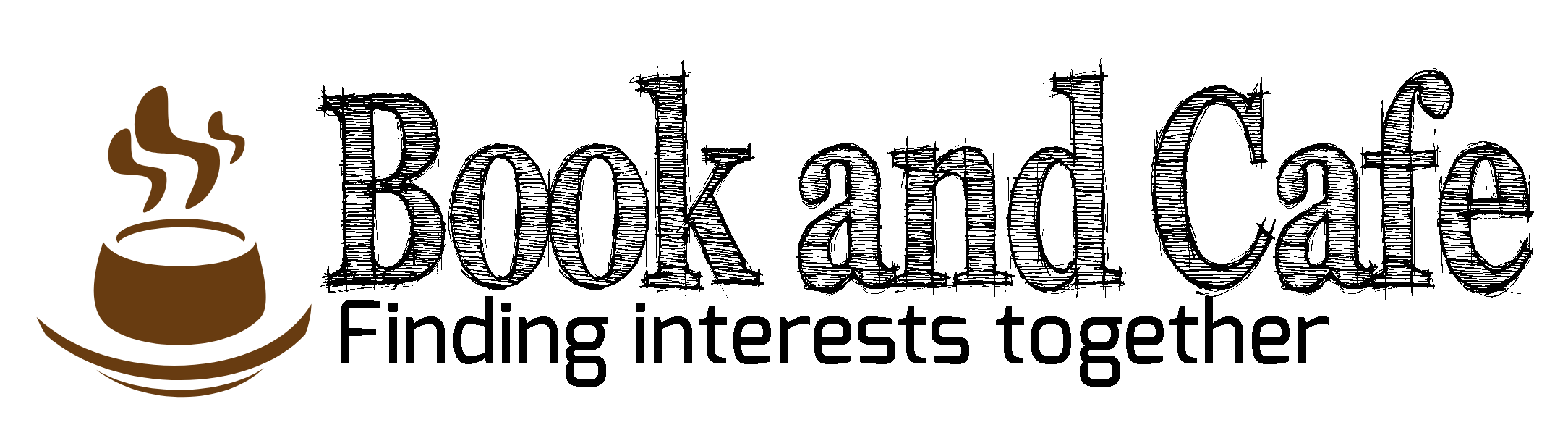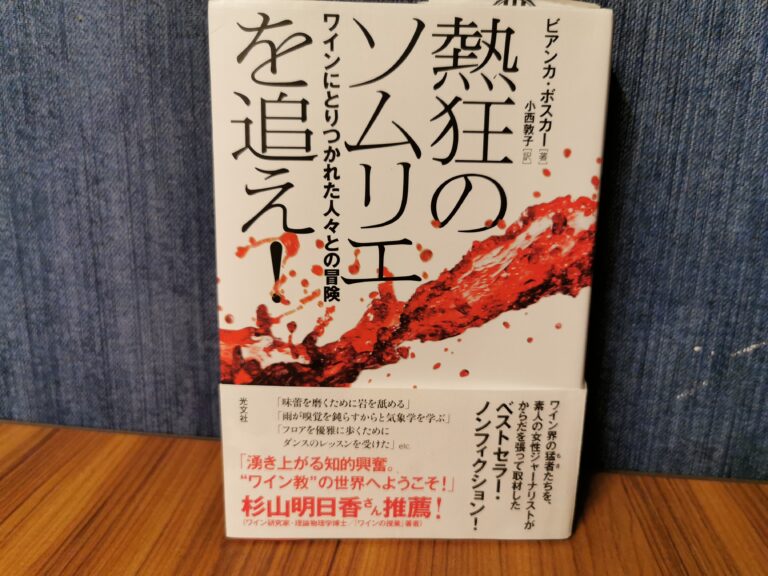【内容】
著者のビアンカ・ボスカーは『ハフィントン・ポスト』でテック担当の上級編集者をしていた。華やかな世界に身を置くビアンカはある日、レストランでソムリエの世界大会があることを知る。
そしてソムリエたちはその大会に勝つために、ありとあらゆる香味を体験し、味覚や嗅覚のトレーニングのヒントや学びを請うため天候の専門家や調香師へ会いに海外まで行くらしい。
この話を聞いたビアンカはワインの何がソムリエを熱狂させるのかを知りたくなる。さらにそんな彼らのワイン体験を自分も味わうことはできないだろうかと思うようになる。そして、そのためには彼らの取材だけで足りるだろうか。彼女の答えは明白だった。それは安定して栄誉ある地位を捨てソムリエたちの世界へと飛びこむのだった。。。
といっても、テック担当の編集者だったビアンカのワインに対する知識は圧倒的に足りていない。それでもワインの試飲を重ね、知人のつてをフルに活かしてレストランでワイン・ラットとしてのポジションを得る。ワイン・ラットは文字通り、ワインセラーをせわしなく動き回る下っ端ポジション。今までのように煌びやかな世界ではないかもしれないが、彼女の本当の旅はいよいよここから始まった。
ビアンカは先輩ソムリエの指導を受け、また信頼できるメンターを得て、少しずつワイン業界に知っていく。そしてとあるワイン・テイスティング会に入会すると世界はさらに広がる。知らなかったビンテージ・ワインを飲み、その味に関する表現を学ぶ。その味わいは土壌からくるものなのか、天候か、それとも製法なのか、ワインを愛する同志との考察も重ねるようになる。ビアンカはさらに様々な専門家、例えばアロマの専門家、調香師、醸造家、希少ワインコレクター等々。とにかく持てる伝手と取材根性をもって世界を訪ね歩く。
好ましい出会いもあればそうでないものも。果たして、彼女はソムリエたちのことを真に理解できたのか、そして彼らの仲間として迎え入れられたのか。これはワイン業界に飛び込んだジャーナリストがその歩みを克明に描いた本でだった。

ビアンカ・ボスカー 光文社 2018-09-13
【内容を振り返りながら感想】
全体を通して

畑違いの分野から転身したからこそ見えるものがあると思います。もしくは彼女が本質をよく見極められる人だったからかもしれません。この本ではワイン業界の明暗がとても鮮明に描かれていました。
良い面、それはソムリエはワインをこよなく愛し、その理解のために人生をかけていることがわかること。さらに、良質なワインをお客さんとも分かち合いたいと思っていること。悪い面、それはソムリエが多くの人同様にノルマを抱え、良いワインを薦めるに値するかきちんとみているということ。それらが職業の描写とともに丁寧に描かれています。
そして、ワインを趣味にしようか悩んでいる人にぜひ読んでほしい点として、ワインを理解することによって(ワインでなくとも飲食の何かを好きになれば)、人生は豊かになるということについても語られていることです。読むにあたって注意を促すとしたら、訳書なのですこし読みにくい点があること、また本筋であるビアンカのワインの旅路とそのほか多くの寄り道が幾分か複雑に行き来するため、その分、やっぱり読みにくいのかもしれないと思える点はあるかも。
ただし、それを差し引いても味や飲食という分野に興味を持つ人にはお勧めしたい一冊です。ということで、以下に個人的に良かったポイントを3つにまとめましたのでよかったら読む際の参考にしてみてください(以下、ネタバレも含むので知識ゼロで読みたい方は読後に読み進めていただければ幸いです)。
ビアンカが魅せられた世界と自身の成長
最初の章でビアンカはいわゆるエスタブリッシュメントとしての友人とレストランで食事をしている際の描写があります。そこで話される会話はそんなに面白くもないし、食事に対しても大して興味があるように思えません。さらに登場したソムリエの話もピンときません。それどころか、このころの彼女はソムリエというのは適当なことをいって法外な値段のワインを売りつける人というイメージを持っています(笑)。
そして、家へ帰るとSNSやネットを介して大会やソムリエのことを調べ上げて、もしかしたら自分にもできるかもという、よくわからない自信(いや、ほんとうにそうなんです)から、職を辞めてしまいます。
やがて彼女はソムリエと行動を共にし、自身もソムリエ試験を志すことになるわけですが、その過程でソムリエが日々自身の給料の多くをワインに使って、様々なワインの味を覚えていることについて知ることになります。それどころか、プライベートな時間を削って香りの勉強をしに調香師が行っている香りのトレーニングに通ったり、給仕する際の姿勢を改善するためにダンスレッスンに通ったり、表現のために美術館や劇場巡りをしている人がいることを知ります。
それらの行為はもちろんキャリアのためでもあるのですが、究極的にはお客さんがワインの味を理解できるように自分の表現方法を学んでいるということを彼女も理解するのです。それはかつて自分も揶揄していた大げさなワインの表現は必ずしも自分向けではないかもしれないけど、それらの表現方法を好む人はいるし、そのほうが理解しやすい人もいるということに気づかされるんです。
最後に彼女はすっかりワイン狂の一員としてかつては自分が誘われていたような文言で読者にワインを薦めてきます。そしてワインがいかに人生に有用かを説いてくれています。読者は苦笑いでビアンカがミイラ取りになってしまったことを知るわけですが、そのカタルシスが何度読んでも心地よくもありました。
ソムリエのキャリアと苦悩

この本ではビアンカのソムリエ修行についても描かれています。それは目も当てられないほど悲惨なものでした。当然、編集者としてのキャリアはここでは描かれず、その観察眼が光ることも。。。。あまりなかったように思えます。ただ、役立ったものとしては言語と味をリンクさせることでした。ソムリエはワインの味を表現する際によくほかの果物や食べ物に例えるますが、それには多くの味を知り、それらをトレーニングして記憶として定着させなければいけません。その際、彼女の語彙力、もしくは言語に対する理解力があったことが一定の役に立ったとしています。
いずれにせよ、そのようなことはごく一部です。
彼女は職場でデカンタージュは失敗するし、オーダーもミスする。ワインをこぼすことなんて日常茶飯事。結構な状況に陥っているシーンを本書内で垣間見られます。それでも先輩給仕たちに食らいついていきます。その図太さは勇気をもらえる、、、、いや見習うべきものだとも思えます。
やがて、彼女は職場を変えていきます。この辺は極めてアメリカ的だし、現実的なところでもあります。というのも、最終章、ソムリエ試験をともにするアニーの職場と比較することでよくわかる仕組みになっています。ノースカロライナ州のレストランでウェイトレスとして働くアニーはとても優秀で向上心もありました。やがてどのお酒を入荷すればよいかも任されるほどに信頼もされるようになりました。ただ、このレストランでは高額のワインは注文されません。利用者が質より量を求めるから。ということは、ソムリエ試験のテイスティングで出てくるかもしれないワインは自分で求めないといけません。経済的に余裕のない彼女にとってそれは非常に難しいこと。また、優秀な指導者とも出会うことはかなわないのです。
だからこそソムリエは身銭をきるか、それともより良い職場に身を置くしかないのです。もちろん、良い職場に転職するのも難しいことです。本書でも紹介されていますが、『NYでソムリエとして働くためにはNYでのソムリエ経験が必要』とか。まるで禅問答のようなキャリア形成が求められるのはどこの世界でも同じようです。そのため、自分を売り込むために日々の努力は欠かせないのです。故に向上心のない人は本質的にソムリエには向かないのかもしれません。
ソムリエになれたとしても、今度はその職位にあったノルマが課されます。NYの不動産賃料は高く、もしかしたらオーナーからのプレッシャーからかもしれません。いずれにせよ、レストランの1/3の収益源が飲み物からだとすると、ソムリエに課されるノルマも小さくはありません。その結果、客を事前リサーチして、場合によっては詳細に区分するようになります。”ネットによれば××(肩書等が××には入ります)”、”(超)金払い良好”、”前回トラブルあり”、”プレス関係”等が代表的な呼称らしいです(笑)(詳しくはP185、6あたりを読んでください。ここだけでも十分に面白いです)。もちろん、ソムリエも金払いの良いお客につきたいと思います。そうすれば、瑕疵がないか確認する際に味見ができるから。
でも、レストランを訪れる客はそんな乗客だけではありません。ソムリエは必ずしもノルマにプラスにならない人たちにも最適なワインを選んで満足してレストランをあとにしてほしいと願っていることをきちんと描いています。ただし、そのためにはお客さんにも誠実でいてほしいとも。この辺は客として守りたいレストランマナーにも通じるところで、非常に興味深かったところでもありました。
専門家とのやり取りを通して得られる真実
色んな専門家と会って、ワイン業界の良い面、悪い面を学びます。と同時に多くの誤解についても解いていきます。例えば、世間でよくソムリエを批判する際に使われる”ソムリエは赤ワインと白ワインを区別できない(論文リンク)”という論文について触れます(P165~)。
そもそもこの実験の被験者はソムリエではなく、醸造学部に在籍していた学生だったという。しかも、白赤について選ぶものではなく、白赤(赤は白ワインを着色したもの)の各々のワインから感じ取れるフレーバーを述べよというものだった。結果として白からは白らしい「リンゴ」「ライチ」「グレープフルーツ」が感じられたといい、赤からは「カシス」「ラズベリー」「プルーン」のようなものが感じられたという。
この実験からは専門家が味を見分けられることができないということではなく、ワインに精通した人も多くの外部情報に引っ張られるということだったという。それが、わかりやすく、しかも人々が懐疑的に思っているであろう部分を取り出してミスリードしていると解説しています。
この一つのエピソードだけでも十分に面白いところですが、これらの検証や論文に関する考察をいくつか行われています。また、専門家の考察についてもきちんと取材して明かしてくれます。それらのいくつかはもしかしたら読者の誤解を解くきっかけや新たな知識をくれるものになるのではないかなと思います。
ということで、この本はビアンカの成長日記でもあるし、ワイン業界の暴露本でもあるし、トレビア本としての側面もある本なのです。どれかにピンときたら、斜め読みでもよいので読むことをお勧めします。
本の概要
- タイトル:熱狂のソムリエを追え!ワインにとりつかれた人々との冒険
- 著者:ビアンカ・ボスカー(HP X insta) 訳者:小西敦子 (X)
- 発行:光文社
- 組版・印刷:新藤慶晶堂印刷
- 製本:国宝社
- 第1刷 :2018年9月20日
- ISBN 978-4-334-96224-1 C0077
- 備考:【原題】Cork Dork A wine-fueled adventure among the obsessive sommeliers big bottle hunters and rougue scientists who taught me to live for taste (2017-06-08)by Bianca Bosker
- Page 147 12行目 銀行家(バンカー)イルカ?? Pierre Paul Brocaの調査に関して
- 最新作:Get the Picture: A Mind-Bending Journey among the Inspired Artists and Obsessive Art Fiends Who Taught Me How to See(2024-03-07)
関係サイト
次の本へ

鹿取みゆき、虹有社、2013-10-02
だいぶ前の本になってしまいますが、ワイン関連本を一冊。この本は香りやうま味の専門家、ワイン醸造家、そしてジャーナリストが各自の専門分野からワインのにおいと味わいについて解説したものです。ビアンカの本が体験記となっているのに対して、この本は細かいトピックごとにまとまってて読みやすいです。また、ビアンカのほんの一部をより詳細かつ分かりやすく解説している部分もあるので、理解を深める観点からもお勧めできます。
雑な閑話休題(雑感)
ワインを楽しまなきゃ損な時代

国税庁が実施した酒類製造業及び酒類卸売業の概況(令和5年アンケート)によれば、日本には468のワイナリーが存在します。みなさんの想像より多かったでしょうか?ちなみにこの調査の5年前に実施されたものでは331。つまりこの5年間のあいだでワイナリーの数は1.5倍になっているんです。国内ではアルコール消費の低迷が世間ではよく話されますが、一方でワイナリーブームがあったというのは事実でしょう。
その恩恵は色んなところで確認できます。地産地消を追い風に地元で生産されたワインを飲んだり、農園も運営しているワイナリーの見学ができるようになったりと。かつては生産国までいかないとできなかった体験の一部ができるようになりました。もちろん、その体験の中にはテイスティングやペアリングがあります。
この本を読んでビアンカが経験したかけらでも体験してみたいと思ったら、身近なワインショップやワイナリーツアーに申し込んでみてはいかがでしょうか。個人的におすすめなのはサントリー登美の丘ワイナリーが行っているものです。有料のツアーになりますが、サントリーがその土地で行っていることや歴史、品種ごとのテイスティングが行われます。また、有料であるため、ワイナリーでのワイン購入のプレッシャーもありません。もちろん、隣接する販売会場では様々なワイン販売が行われているので、お好みで購入することはできます。
いずれにせよ、この本がきっかけとなってワインに対する見方が変わる人もいるかもしれません。それに限らず、今まで摂取していた食べ物や飲み物に対する接し方が変わるということもありえるかもしれません。そうしたら、著者のビアンカもうれしく思ってくれるんじゃないでしょうか。そんな人が一人でも増えるといいなと思いながら、今日も参加しやすいテイスティング会がどこかにないかなと思いながら、ネット検索をする自分でした。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。また、次の記事でお会いできるのを楽しみにしております。