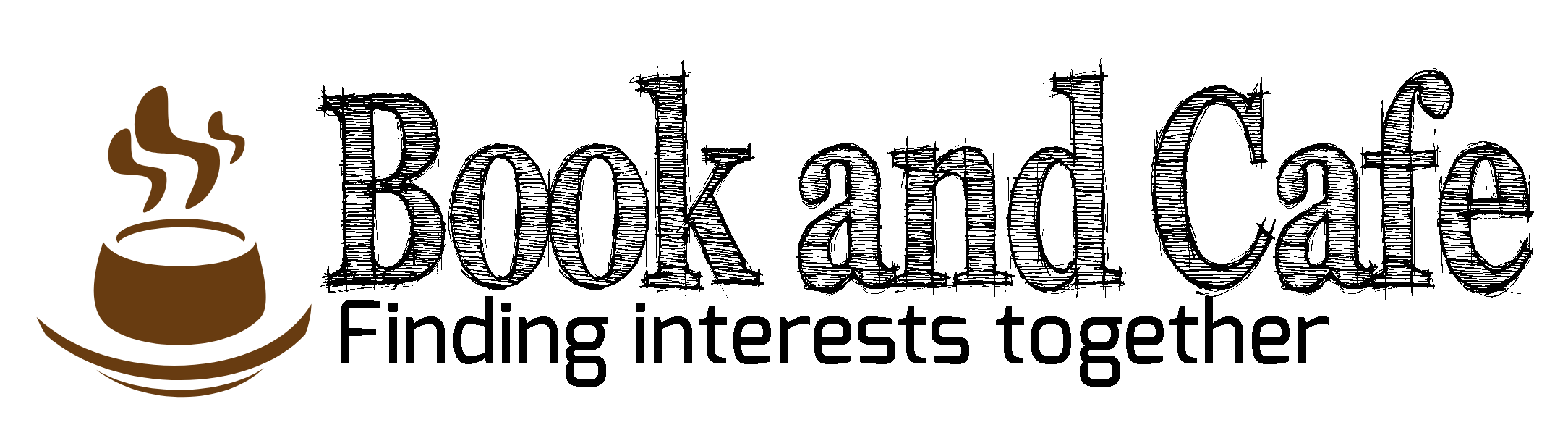あらすじ
12歳のグレイソンは物静かでクラスでも目立たない男の子だった。両親は交通事故で他界し、叔父と叔母に引き取られていたけど、ぐれることなく、引き取り先でもうまく生活をしていた。
そんなグレイソンの趣味はお気に入りの服を着た自分を想像したり、教科書の端に可愛い絵を描くこと。それでも成長するにつれ、お気に入りの可愛い服はだんだんと自分には合わなくなってくるし、教科書の端に描く絵は男の子が描くにはふさわしくないのかもしれないと感じることが多くなった。
そんなグレイソンに一つの転機が訪れる。大好きな人文学のフィル先生が顧問を務める演劇部がキャスト募集を始めたこと。演目は『ペルセポネの物語』。グレイソンは強い意志でその主人公女神ペルセポネ役を志願する。
その結果、グレイソンは色んなことを改めて思い悩むようになる。そして周囲をも巻き込んでいく。住まわせてもらっている叔父叔母、その子供たち。もちろんクラスメイトとの関係も以前のようにはいかない。
果たしてグレイソンはペルセポネ役を射止めることはできるのだろうか。それどころか、大好きなフィル先生のお芝居を成功させることができるのか。そして、グレイソンと周囲の大事な人たちはどうなってしまうのか。
いま、気高きグレイソンの物語が始まる。

ぼくがスカートをはく日 [単行本]エイミ ポロンスキー学研プラス2018-07-31
感想(ネタバレ注意)
いくつかのポイントに分けて本書の中で魅力的と思った点について触れていきたいと思います。
眩しいほどのグレイソンの成長

本書の主人公グレイソンは不思議な魅力を備えた子です。グレイソンは小学6年生、12歳。クラスでは悪目立ちしないようにグループワークの時も最後に残ったメンツに入るような子(そういう行動をとるといじめの対象になりそうだけど。。。)。当然お昼は一人。理由をつけて図書館へと駆け込みます。それが秘密を持ったグレイソンなりの処世術。
でも、同時にグレイソンはクリエイティブなこでもあります。時折、自分の世界に入り込み、かわいい服を着て、好きなところへ行く。グレイソンにとってありのままの自分でいられる、この上なく幸せな瞬間です。でも、その空想も自分の第二次性徴にあわせてうまくいかなくなっていることがわかります。
そんなグレイソンの周囲にも少しずつ波風が立つようになります。ボストンからアメリアが越してきたこと。それをきっかけに女の子グループと少し仲良くなったこと。そのうえで超えられない壁を感じたりします。
その後、グレイソンは学校で行われるお芝居『ペルセポネの物語』のオーディションがあると知り、葛藤を経たうえでペルセポネ役を志願します。そしてグレイソンは見事にペルセポネ役を射止めることとなります。日常的に空想の世界に入り込むのが上手かったからか。それともままならぬ運命に翻弄され、それに抗おうとするペルセポネの心情をよくよく表現できたからかもしれません。
とにかくオーディションでグレイソンは男の子としての偽りの人生からどうにか抜け出そうとするんです。それは冥府から逃れようとするペルセポネのよう。
グレイソンはペルセポネを演じようとすることで、結果的にカミングアウトする形になります。その影響はグレイソンが思った、ただ単純にその役を演じたい、というもの以上の反響となります。そして、グレイソンの環境に大きな変化をもたらします。周囲の対応はもちろん、心ないいじめも発生します。
それでもグレイソンはペルセポネ役を仕上げようと直向きに努力を続けます。ストーリーを読み込み、舞台上で自身をよりペルセポネへと近づけていく。そんなグレイソンを認める人はより認め、見守ろうとしている人はよりサポートしようとするようになっていきます。
グレイソンは舞台の上で輝くペルセポネになるため、多くの困難に直面しつつもやりとげようとする姿は本当に熱く来るものがありました。その過程でグレイソンは成長し、以前とは全く別人物になっているのが文章からもよくわかります。
主人公の成長は児童文学に限らず大きな推進力になりますが、この本でも本当に魅力的な描き方をされていました。
著者はインタビューでグレイソンの年齢を12歳にした理由として、12歳が様々な決断をするまでに少し時間があって無限の可能性を秘めている年齢だからと答えています。
確かに今回の件でグレイソンは多くのことを学び、また多くの力強い味方を得ました。そして世界と自分の正しい接点を見つけたように思えます。今後グレイソンがくだす決断も明るいものなんだろうな、と明るい気持ちにもさせてくれるものでした。個人的にはこの本読むことで、多くの人が同様の明るい未来を迎えるための決断ができるといいなと思う次第です。
グレイソンの支えになってくれた人たち
グレイソンのサポートをしてくれる人たちがこの本では本当に魅力的に描かれています。そしてその登場人物たちが本書を盛り立ててくれています。

フィル先生
まず最初に挙げるべくは何と言っても人文学のフィル先生。彼は学校内でも有数の人気を誇る先生。生徒を思いやり、生徒の自主性を重んじることはグレイソンとの会話の中で表されている通りです。
グレイソンがペルセポネのセリフを読みたいというとき、彼はその意思を尊重しながらも、但し書き的なコメントもしています。それはグレイソンにもフィル先生自身にも言い聞かせるものだったのかもしれません。
その後、フィル先生はPTAや校長先生との折衝等に追われることになります。そのことを本の中では不穏な空気と共に書かれていて一体どうなるの?という想いに一読者としてもなってしまいました。
そして、グレイソンに対するいじめが起こると、授業の教材にハーパー・リーの『アラバマ物語』を用いるようになります。アラバマ物語は子供の視点から黒人差別の理不尽を扱った物語です。それを通じて自分たちがいかに非人道的なことを行っているのかを学んでもらおうという意思が伺えます。いじめに直接的な介入を行っているシーンは見えませんが、それでも存在することを気づき、授業面からもちゃんとケアしようとする。そのうえでグレイソンに送った最後の手紙には。。。ぜひ読んで確認ください。
エヴァンおじさんとサリーおばさん
実父がなくなってからグレイソンを引き取ったエヴァンとサリー夫妻。 事故で両親を失ったグレイソンをいきなり引き受けることになったのだから 、二人も戸惑うことが多かったでしょう。その結果、過ちを犯してしまいます。それでもそれは少なくともグレイソンや家族を思っての行動でした。そのうえで、彼らのできる限りの愛情をもってグレイソン育ててきました。
グレイソンがカミングアウトしてからは二人の価値観に基づいてサポートしようとしました。二人でコミュニケーションをとり、アクションまで起こそうとします。
特にエヴァンおじさんは過去にグレイソンの父親と疎遠になったことを後悔しながら常にグレイソンに優しく接してきました。それは実子が嫉妬を抱くほどに。でも、その誰もに優しい性格があったからこそ、グレイソンは進むことができたことを忘れてはいけないと思います。本当、生みの親も立派なら、育ての親も立派でした。
ペルセポネを射止め損ねたペイジ
上級生で、かつアンドルーやリードと一緒に登場してきたページを誰もがいじめ役と思ったでしょう。しかも彼女はペルセポネ役を目指していたのだから。
でもそんなことはありませんでした。学校では一番のサポート役になってくれました。グレイソンに役者として不慣れなことがあれば教え、孤立していれば輪に入るようにすする。単なる先輩以上の存在でした。グレイソンに限らず、そんな人が近くにいたらどんな人も救いになるでしょうし、そういう人になりたいと思うばかりです。ただ、彼女の優しさの裏には母親がありました。ペイジとその母親はグレイソンのことや父母会で起こっていること、その他多くのことに議論を費やしたことが後に明かされます。それは親子間のコミュニケーションがいかに大切かを教えてくれるシーンでした。
その他にも心優しいお兄さんのジャック、偏見を持たない純粋なブレット、不器用な生き方をしてしまうアメリア。もちろん手紙を介してわかる実父や実母だって魅力的でした。多くの人物が登場する本作、少しこんがらがりそうになる時もありましたが、それでも印象的なキャラクターたちが物語を最後まで飽きさせることなくけん引してくれました。
盛り込まれた多くのテーマ

著者が実際に小学生の先生ということもあるんでしょう。多くのテーマが本作に盛り込まれていました。性自認は大きなテーマではありますが、それ以外にも家族の在り方、グレイソンはもちろん、アメリアの家族は母子家庭です。以前は珍しかったかもしれませんが、離婚率が高まった現在では珍しいことではありません。
また、教育現場と家庭との距離感の問題、これはフィル先生がグレイソンの意思を尊重してペルセポネ役を与えたことに対する反響です。その結果、フィル先生のキャリアは致命的な打撃を受けます。本来であれば、フィル先生の選択は多様性を認めるもので、それ以上のものではありません。それを受け入れられない人のほうに本来は問題があるという話になってしかるべきなのかもしれませんが、そうはならないのが現実問題だし、その指摘も正直酷なのかなとも思えます。いえることは、子供のころから教育現場のみならず、家庭でも多様性に関する様々な議論をする必要があるんだなと思ったことです。
そのうえで、印象に残ったことのが、最後にグレイソンがノートに書き留めた”不安に負けず、大切な行動をおこすこと”です。これは著者がグレイソンに、そして多くの人に伝えたかったひとつのことだと思います。そして、この本に登場する多くの若者たちがとった行動のような気がします。
私自身も今後まだまだ続く不安の中で何かしらの大切な行動をおこせればな、と改めて思える瞬間でもありました。そんなことを思いながら、今回は感想と振りかえりを〆たいと思います。
読んでいただき、ありがとうございました。
PS『ペルセポネの物語』の前年度に上演された『ロラックスおじさんと秘密の種(原題:The Lorax)』、そういえば映画化されていましたね。興味がある方はご覧になってみては?
本について
本の概要
- タイトル:ぼくがスカートをはく日
- オリジナルタイトル:Gracefully Grayson
- 著者:エイミ・ポロンスキー(Ami Polonsky)
- 訳者:西田 佳子( @sazafuku)
- 解説:松中 権
- 絵:まめふく(@mamefuk)
- デザイン:名久井直子( @shiromame )
- DTP:株式会社アド・クレール
- 発行:株式会社学研プラス
- 印刷所:図書印刷株式会社
- 第1刷 :2018年8月14日(本書第2刷5月10日)
- ISBN13: 978-4-052-046-84-1
- 備考: 2016年全米図書館協会「レインボー・ブック・リスト」作品, Originally Published November 4th 2014 by Disney-Hyperion. Discussion Guideと著者インタビュー(PDFリンク(英語))
個人的に興味深く思ったのがタイトルのつけ方。結構ビビッドに変えた印象を持ちました。一目でLGBTに関する本なんだろうなと思えるようなタイトル。原作は”Gracefully Grayson”なのでタイトルからはそういう本だということはわかりません。

Gracefully Grayson [ハードカバー]Ami PolonskyDisney-Hyperion2014-11-04
装幀をみると何となくそうなのかなと思えるのですが、必ずしも断言できるかは微妙。個人的にはGracefulという言葉が極めて宗教的なイメージを持つ言葉だからかなと思ったりしています(God’s grace等に起因します)。ただ、日本ではこれくらいの直接的な表現のほうが望ましいのかもしれませんね。全体の雰囲気を表したタイトルになったような気もします。
本の訳し方はとても繊細でグレイソンの感情や置かれている状況を臨場感をもって伝えてくれたような気がします。さらに装幀デザインが本作のワンシーンをほうふつとさせるもので読み終わった後に眺めるととても感慨深いものになっていました。
また、本作の解説も一つ注目してもいいような気がします。グレイソンがどういう子なのか、松中さんの解説を読むとより詳しくわかると思います。そしてその説明の仕方は様々な人に寄り添って、とても勇気づけられるものでした。
ということで端から端まで楽しめる作品でした。
関係サイト
著者オフィシャルHP: http://www.amipolonsky.com/
twitter: @amipolonsky
エイミ・ポロンスキーさんのHPには最新作情報を含んだ多くの情報があります。自己紹介ページではグレイソンとのいくつかの共通点がみつけられます。また直近の更新はありませんが、ブログも以前はやっていて著者の考えていることや子供たちに対する想いなどが知れます。感じ方は人それぞれだと思いますが、個人的には多くの記事について心に来るものがありました。
ちなみに最新情報や日常の出来事はtwitterがいいかも。微笑ましかったのは本作(日本語ver.)を読んでいる六年生の児童が写った写真が掲載されていたこと。何か嬉しいですね。
次の一冊
さて、ポロンスキさんのもう一つの作品”Threads”は日本では翻訳されていません。彼女のホームページに掲載されているあらすじは面白そうなのでそのうちよんでみようかなと思います。また、2020年秋には新しい作品”Spin with me”をリリース予定とのこと。そちらも楽しみです。

Threads [ハードカバー]Ami PolonskyDisney-Hyperion2016-11-01
ということで今回ご紹介するのは本作の絵を担当されているまめふくさんがこれまた絵を担当されている『クレンショーがあらわれて』です。10歳のジャクソンが想像上の友達クレンショー、そして家族と共に自身の貧困に立ち向かっていくという内容。これも色んなことを考えられる作品となっています。

クレンショーがあらわれて (フレーベル館文学の森) [単行本]キャサリン・アップルゲイトフレーベル館2019-10-04
雑な閑話休題(雑感)

この本はとある本屋さんで見つけてから、その本屋さんで継続的に目撃していた本です。ずっと興味がありました。ただその本屋さんには他にも多くの魅力的な本があり、またそれ以上に多くの新刊にも興味を奪われていました。
そして昨年の暮れ、同じ本屋さんでようやくこの本を購入しました。読んでみるとなんで今まで先延ばしにしていたんだろうというほどに引き込まれ、すぐに読み終えてしまいました。
今回手に取った本は第2版でした。当初目にした本と一緒なのかどうかはわかりませんが、この本を置いといてくれたその本屋さんには感謝しています。
みなさんもそんなエピソードありませんか。個人的にはいくつかの本屋さんでそういう本を抱えています。いつか買うかもしれないし、永遠に買わないかもしれない。本の出会いは色んな人に支えられつつも、運命的なものなのかもしれません。