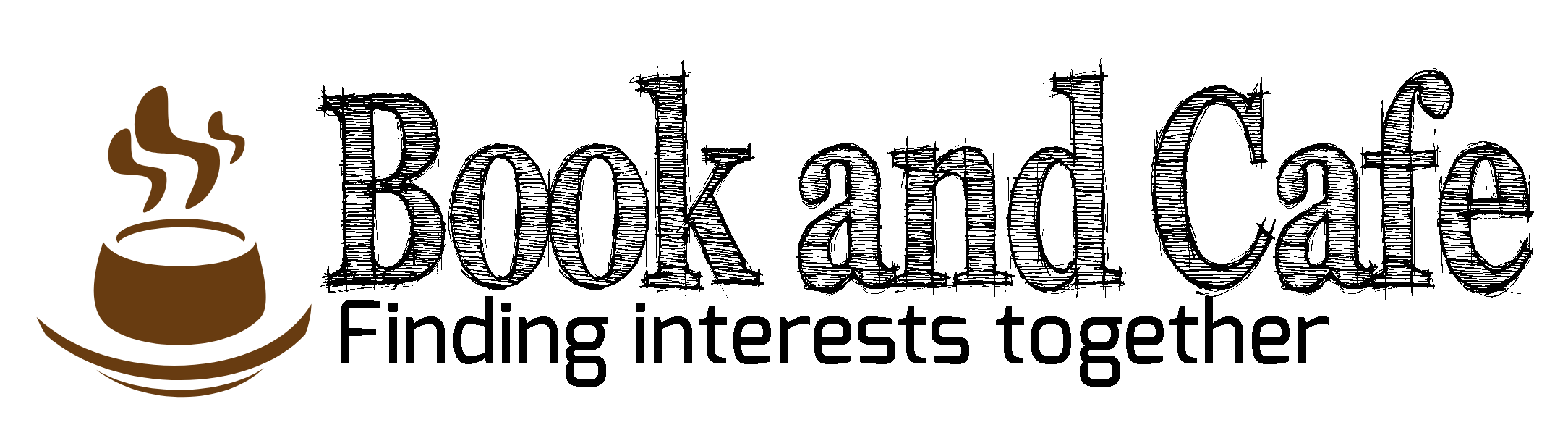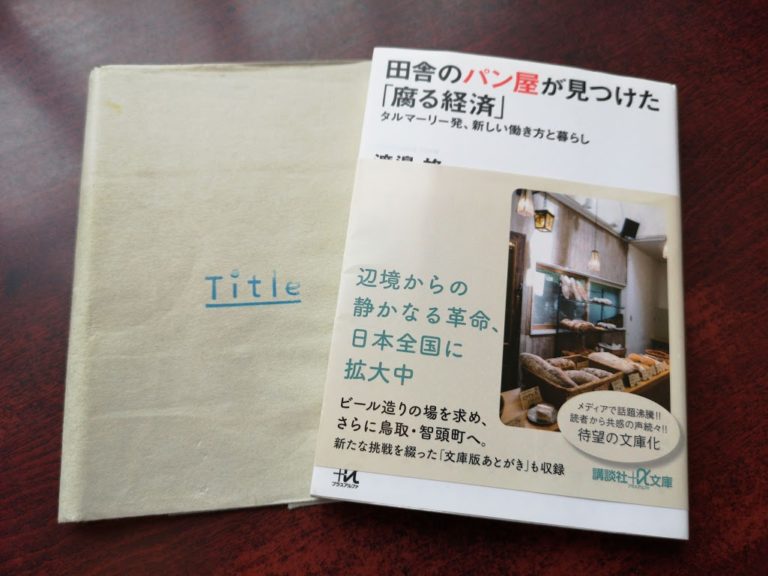【内容】
高校卒業後、フリーターを7年間経験、その後大学に通って30歳で新卒社会人となった本書の著者渡邊格さん。彼が就職したのは父に紹介された有機農産物の卸販売会社だった。渡邊さんはそこで行われる業界の商慣習や納入業者とのもちつもたれつの関係に世間への疑問を深めていくこととなる。
そして、とある日渡邊さんの寝枕に現れた祖父は「イタル、お前はパン屋をやりなさい」といったそう。そんなふうに運命に導かれるようにパン作りの道に進んでいく渡邊さん。ただ、この彼を待ち受けていた道のりは大変に険しいものだった。寸暇を惜しんで世通り作らなければならないパン。それなのに暮らしは湯田金物とは程遠い。食い違う天然酵母の基準や添加物不記載の実情。渡邊さんの疑問はやがて確信に変わり、この問題に何かできないかと考えるようになる。
渡邊さんは様々なパン作りの現場を渡り歩いて、ついに自身のパン屋を開くことになる。その過程で知ったパンに関するあれやこれ、そしてパン屋で働く過程で考えたこと、なぜ都心ではなく、田舎でパン作りをしているのかについて書きまとめたのが本書です。
色んな価値観が飛び交う今だからこそ、じっくりこういう本を読んで自分の価値観を広げてみるのもいいと思います。正解は一つじゃないはず、そんなことを教えてくれる一冊です。

田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」 タルマーリー発、新しい働き方と暮らし (講談社+α文庫)渡邉格講談社2017-03-31
内容をまとめながら、時に感想
前提となる読者としての私の立ち位置

この本は第一部、とりわけ第1~3章までに書かれていることとそれを総括し、またタイトルの解説をしている5章の考え方が特徴的でした。ここに納得できるか、もしくは納得できないにしても著者の言い分に寄り添えるかが大きな分かれ目かも(考え方の問題なので賛同できない、もしくは違うと思う人はいると思います)。納得すれば、読書の大きな推進力になるでしょうし、できなくとも、あなたの隣人の考えを理解する一助になると思います(ご自身がこう考えなくとも、こういう世界に関与してみたいと思う人は多くいると思いますので)。
ちなみに私はどちらかというと後者のほうです。多くのことは理解もできますし、内容は楽しく読めました。また、働く側からみても色んなところで共感できますし、突き詰めていくと代替不可能なことをやろうよ、あなたにしかできないことをやろうという感じで、どんな分野でもいえることをパン屋の専門技術等に置き換えていっているものなので理解もできます(この主張は一部しかカバーできていませんが、ここが一番他でも実践できるところなので、こう書きました)。
ただ、少しだけ、もう少しだけ資本主義や自由主義経済がもたらしたものにも目を向けてもいいのかなと思ったりします。もちろん、渡邊さんがそれらを全く否定しているわけではありませんし、その上に自分たちが成立しているのも認識されたうえでの主張なのは承知しています。確かに本なのでどうしても主張を明確にする必要はあるのですが、少しばかりそこにしこりが個人的には残ってしまいました。
ということでそんなあいまいな立ち位置の人が以下、まとめながら振り返っているんだと思ってください(普段はあくまで著者の意見をまとめているだけですが、この本の場合、もしかしたらバイアスがかかってしまうかもしれないと思い、事前に自分の立場について説明してみました。)。
会社から飛び立つ渡邊さん

渡邊さんの経歴については本書内で少しずつ明かされています。バブル期に高校卒業し、そしてアルバイト生活をしながら生計を立てていました。いわゆるフリーターです。当時はバブルが過ぎたといえど、なんとなく大丈夫な風潮があったんだと思います。そしてそんな空気間の中、父親の仕事について94年、23歳の時にハンガリーでしばらく暮らすこととなります。なかなかユニークな生い立ちです。そんな渡邊さんはハンガリーで2つの体験をします。
一つ目は多くの食べ物が自然由来だったとのこと。まだ社会主義国から資本主義へ移行したばかりといってもいいような状況下で人々は添加物や防腐剤と無縁の生活を送ることができたといいます。これによって日本に帰ってから感じる味覚が大きく変化したと変わっています。
そしてもう一つが、自分が何者でもないと痛感したこと。当時ハンガリーを訪れていた日本人は会社員にしろ、留学生にしろ、何かしらの目的をもって訪れていたそう。一方で、父親の付き添いで訪れていた渡邊さんは自身の身の上について再考することになります。結果、帰国後の就学へとつながります。そして、後の就職へ。渡邊さんのキャリアの築き方はもしかしたら今の時代にぴったりなような気もします。人生100年時代。色んな経験を経て就学・就職へ。その中で自分なりの社会との接点を見つけるというのはコストも時間も書ける必要がある分、贅沢かもしれませんが、自身の納得感を伴うものではないでしょうか。
ただ、渡邊さんの受難は続きます。就職した有機農産物を取り扱う会社は必ずしも”良い”会社とは言えませんでした。産地と異なるところで行われる野菜のパッケージング。販路の見つけられなかった野菜の大量処分、社内のガバナンスは必ずしも構築されてなく、恣意的な指示もとぶ。。。多くの社会経験をしてから入社した渡邊さんからは耐えられない状況だったんだと思います。
一方で良いことも。この会社で志を一緒にする伴侶真理さんと出会います。真理さんへの信頼と感謝の気持ちは本のいたるところから読めます。素敵な夫婦なんだろうなと想像しながら読むとそれだけで気持ちが温かくなりました。
少し脱線してしまいましたね。
そんな心強い味方を得ながら、夢枕で聞いた”お告げ”を胸に社会への再スタートをきることになります。2章は渡邊格さんと真理さんのお店を開業する前後の様子、少し幕間のようなエピソードです。ただ、ここはここで開業する誰もが直面する問題がわかりやすく描かれている気がします。そして3章以降に渡邊さんの社会経済講座へと続きます。
マルクスと労働力についてパン屋で考える

パン屋での労働環境は過酷だということはよく知られています(他の仕事も過酷ですが、種類が異なるものです)。ちなみに以前、深夜にジョギングをしていたころ、某有名高級パン屋さんの前を通ったのですが、明かりが煌々とついていて従業員の方がパンの成型っぽいことをしていたのが印象的でした。渡邊さんも同様に深夜2時から働くことに。しかも朝ご飯は適当に片手間で食べるしかないほど時間との勝負になっていたそう。
ちょうどその頃、親の勧めもあって読み始めていたカール・マルクスの『資本論』。そこには19世紀のイギリスのパン屋の労働環境の過酷さが指摘されていて、自分のことのように読みふけったそうです。もともと19世紀以前のイギリスのパン屋は職人組合に属することが義務付けられていました。そして、独立する場合も職人に認められる必要がありました。
ただ19世紀半ばになると人口増加や農業改革がなされ、そのうえで資本家が登場。だんだんとパン業界にも関与を強めたとされます。その結果、職人組合のパン屋とそうでない安売り業者(アンダーセラーズ)が登場しました。後者は労働者を酷使し、その分多くのパンを製造することによって利益を最大化していました。ただ、そのような労働環境はパン屋だけでなく、他の多くの現場でみられました。ここでは少し表現を丸めました。渡邊さんはもう少し辛らつに書かれているのでぜひ本書を読んでみてください。その批判的熱量が伝わると思います。
さて渡邊さんはここで初歩的なマルクス経済学について以下のように簡略して紹介しています。
1.マルクスがいう「商品」が「労働によって作り出され」、「使用価値があり」、「交換できるもの」だと定義します。これによってパンが「商品」だということが認定できます。なぜなら、二つの条件を満たすからです。
2.「商品」の「価格」決定のメカニズム。「商品」としてのパンが手元にあったとしてほしい衣類とどの程度だったら交換してくれるか。パン職人はパンだけでは生きていけず、これを交換する必要があります。マルクス経済学では価格は需給では決まらず、労働を”平準化して”推測される「交換価値」を用います。
3.そのうえで労働者が得る「給与」は、労働者が資本家に提供する「労働」の対価であり、「交換価値」によってその「価格」は決定します。本来、労働者は自分の暮らしを再生産(維持・拡大)するためにそれに見合う「価格」を求めることが想定されますが、代替可能で平準化された「労働」の場合、資本家の推定する「価格」の「交換価値」は低くなります。結果として、「給与」には下方圧力がついてまわります。
4.資本家は「労働力」やその他のコストを投入して「商品」を作り、その売り上げから「利潤」を得ます。そのため、「労働力」を含むコストを低く抑えることが自身の「利潤」の最大化へとつながります。
5.マルクスは、労働者にとって「労働力」が正当な「価格」であり続けるためには①個人の自由が保障されていることと、②労働者が「生産手段」を持つ場合だと主張しています。ここでいう「生産手段」とは生産設備や機械のことを指します。
つまり、これらの条件が満たされない限り労働者の「労働力」は買いたたかれる可能性があるとマルクスはいうのです。これらを学んだ渡邊さんはいよいよ自身にあてはめようと四苦八苦する日々が始まります。
(長くなってきたので改ページ!たぶん折り返しくらいのイメージです)
- 1
- 2