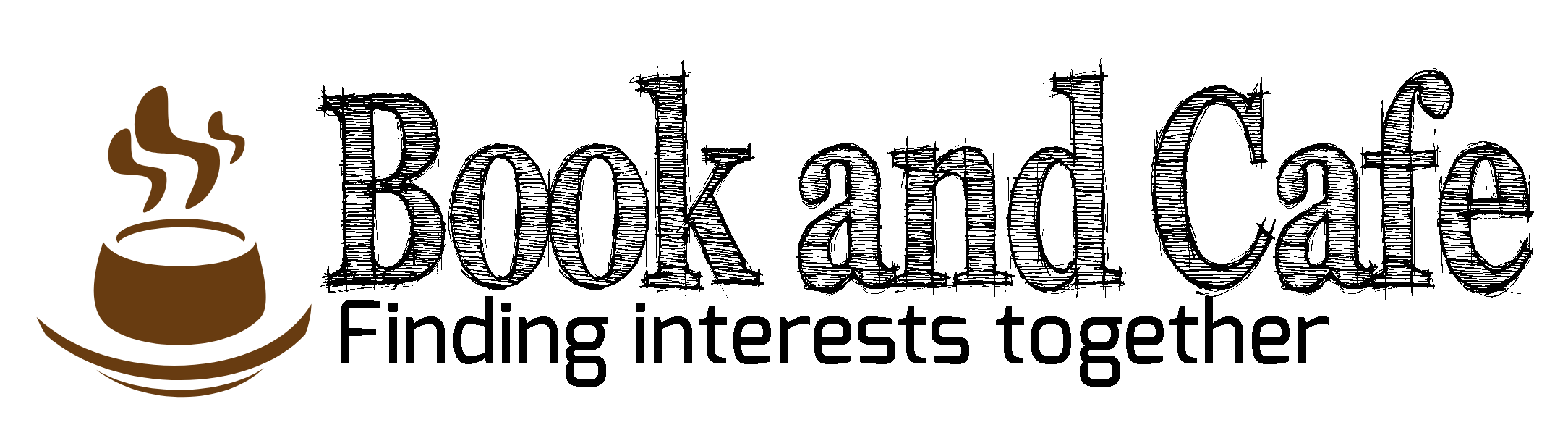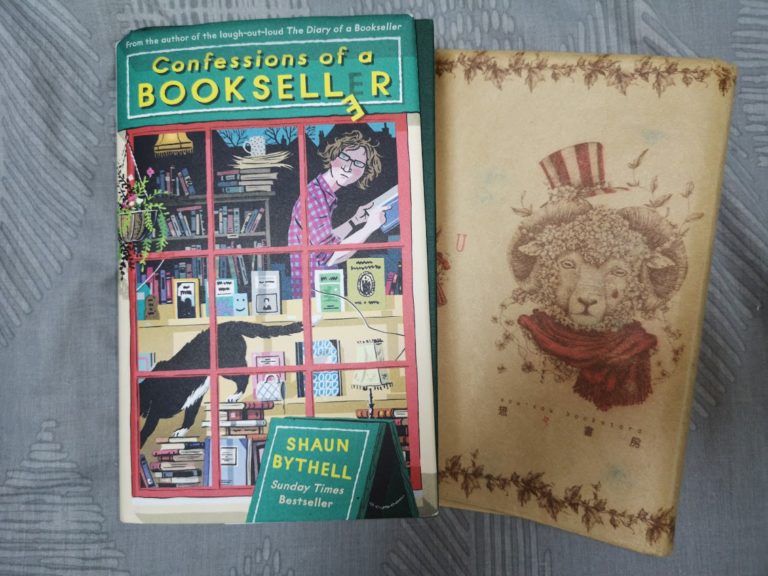内容を振り返りながら感想
本書は本屋さんの日常が主題なので、抱腹絶倒な出来事やミステリアスな事件は起きません。基本的にはお店や人との出会いをショーンさんを目を通して感じるというものです。
ただ、ショーンさんの語り口はユーモラスなので読んでいても苦になることはありませんでした。読んでいるとまるでショーンさんとカウンターに立っている気分になれます。その際、何となく彼の思いが憑依してお客さんを眺めたり、書棚を整理したり、AmazonやAbeからのオーダーに対処している気分になれました。時に面倒くさいお客さんの描写があると塩をまきたくなるし、常連さんの滞在が描かれると心が躍ってしまいます。そんなふうに楽しく1ページ1ページをめくることができました。特に以下の点が個人的には気に入ったポイントでした。
登場する個性的な人々(店員もお客さんも)

この本を彩るのはなんといっても店に関わるユニークな人々です。
アンナはかつての戦友でパートナーでした。今もウィグタウンのブックフェスティバルを盛り上げたり、店のサポートのために足しげく通ってくれ、頼りになる人。そんなアンナを慕う店員のニッキー。彼女は時々時間にルーズ、でも本に対する嗅覚はショーンさんより優れているときもしばしば。独自のセンスで需給を踏まえた値付けのできる人です。フィオナは寡黙だけど、黙々と乱雑な店内を整理整頓してくれる欠かせない人材です。イタリアから自薦でインターンに応募してきたグラニーは、とんでもないものをキッチンでよく作りますが、お店を賑やかにしてくれます。ほかにもパートタイムで働く個性的な面々、いずれも対等なパートナーとしてお店を盛り上げてくれているんです。
そして、お店にやってくる色んなお客さんたち。古書店がぼった食っていると思う人々、当然のようにディスカウントを求める客、店内や本の写真だけを撮って帰ってしまう客、ここまでくると絶望的にもなりかねませんが、でもそんな客ばかりではありません。名前も知らないし、口も交わしたことない、でも毎回数冊の本を黙って会計していく常連客に心を救われ、アマゾンで注文することを避け、わざわざお店に利益をおとしにきてくれるお客さんに胸が熱くなります。色んなサポーターによって支えられているのが『The Bookshop』です。
もちろん、ブックフェスティバルの中心であり、著作で有名になったショーンのお店には世界中からお客が集まってきます。英語圏が多いようですが、ドイツやフランスといった大陸からのお客さんもしばしば登場しています。さらには遠くアジアからのお客さんもいました。そして、そんなお客さんから帰国後送ってきたお便りが届くこともあるようです。その人たちが買う商品も様々。そんな人たちがどんな本をかうのかな、なんて想像しながら読み進めると面白いかも。
現代において古書店を経営するということ
この本は読者を古書店業界へ勧誘する本でも、礼賛すべきと誘導する本でもありません。」
ショーンさんのお店はオンラインでの売り上げはシステム的なトラブルに見舞われない限りある程度たっているし、実店舗にある程度の人を呼び込めていますが、経営は必ずしも順風満帆ではないようです。
貧乏に関することは日記の中でたまに触れられています。例えば、ペーパーバックのディスカウントを求めてくる人たちが明らかに自分たちより裕福なのはどうにかならないのか、とか。少額の本一冊を買うのに自分を1時間以上拘束されてはかなわないとか、まぁ、少し感じ悪く映るかもしれませんが、ボランティアや慈善事業で行っているわけではないので当然のことですよね。
また、本の売買はオンライン取引の登場によってやりづらいことになったとも記しています。人々は全く売れていないオンラインでの価格を参考にしてもっと高く書いとれるはずだと主張するようになります。また、買い取らない本についてはショーンさんが商売の機会を失っているとののしることも。とにかく、やりづらいことがたくさん。もし本当に儲けたいのなら、古書店の経営なんてしない、とも言い放つくらいです。
あと自身のことではないですが、Oxfam bookstoreについてもなんともやりきれない気持ちを抱いています。
Oxfam は食糧問題を中心とした貧困撲滅を目的としたNPO法人です。Oxfamが行う資金調達手段の一つとしてOxfam Bookstoreがあります。Oxfam Bookstoreは寄贈された本をボランティアスタッフが販売します。また、営利法人ではないため税金の優遇措置もあります。書店が近隣に存在する場合、Oxfamは値段について一定の配慮は行うとしているものの、消費者からすれば必ずしも使い分けが行われているわけではありません。そのため、長期的に見れば近隣に進出された中古書店が退出を余儀なくされる場合もあるんです。別にOxfamの活動そのものを否定したいわけじゃないのですが、何となく世知辛いなぁとぼやくのです。
Embed from Getty ImagesさらにアマゾンやAbeの登場で中古書店の経営に追い打ちをかけます。一部の初版本や希少本を除けば、ペーパーバック等に引っ張られ、ほとんど二束三文でしか売れなくなったそう。加えて、そのペーパーバック等の一般書籍だって品質は千差万別なのにアマゾンでは必ずしも反映しきれていない。にもかかわらず、最低価格のものが取引され、顧客は品質に文句を言い、引き取りを要求するという。仮にこの要求に応じないと低評価がつくのはよくあることだそう。。。
彼の本屋では希少本のブックカバーなどを修理して販売するというものも行っていますが、そのような手間をかけてもその行為を評価する人は以前に比べて減ってしまったという。さらにそういう本を収集している人たちはもうほとんどいないとも。そこまでしても得られる利益は限定的だそう。
また、仕入れ先もだいぶ変わってしまったみたいです。以前はそれでも前向きな処分があったようですが、最近は老夫婦が老人ホームに入居する際に処分するために呼ばれたり、遺産相続で本を引き継いだものの、その人にとっては必ずしも必要としていなかったりと。
これ以外にも様々なエピソードが吐露するように書かれていて、いろいろと考えさせられるものばかりでした。本を読みながら何かできないか考えるのも面白いかなと思います。
スコットランドの地方都市で暮らす

この本のもう一つの魅力はショーンさんがスコットランドを愛しているということ。それはショーンさんがこの街で本屋を開業したことからも間違いないことだと思います。
日本同様に四季を感じられる日々。春の訪れを庭に芽吹く緑に感じ、じめじめした梅雨の訪れに、短い夏を予感し、その夏が終わるのをアフリカ大陸に行こうとする雁や燕の様子で察知、飽きに行われるブックフェスティバルの準備をして、クリスマスにやってくる友達たちを慌ただしくもてなすショーンさん。どれもいとおしく感じられます。
さらにショーンさんは山登りにも行くし、渓流釣りもする。友人とバーで飲んで翌日は二日酔いで店を開けるのが遅れることも。。。。なんともスコティッシュじゃないですか。この合間に少しだけスコティッシュイングリッシュを感じられる場面もあります。それも雰囲気がでてていいんです。
ちなみに、これらについては今ならではの楽しみ方があります。それはYoutubeで公開されているうぃぐたん関連の動画です。著者のショーンさんはもちろん、その他にもブックタウンフェスティバルの動画、街を訪れた人々の動画があります。また、ショーンさんのFacebookを通じて日々の様子はもちろん、写真や動画もよくアップしてくれています。実はこの日記が書かれた2015年についても同様です。特に本書内でも話題になっている店先に置かれる黒板の写真は本書内の出来事を思い出してくすりとしてしてしまうかもしれません。
そういう情報を使うと未だ訪れたことのないウィグタウンもより身近に感じられるかもしれません。ちなみに下に張り付けたYoutube動画では”The Old Bank Bookstore”が紹介されています。そう、”The Bookshop”以外にもたくさんの魅力的なお店を抱えるのがウィグタウンという街なんです。