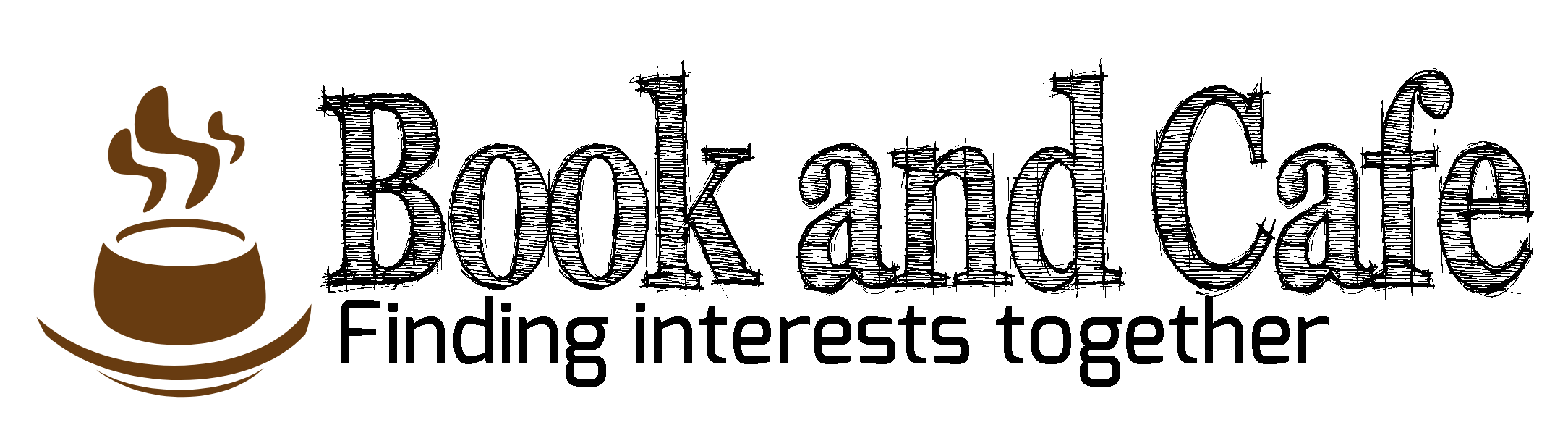ストーリー
舞台は1959年、イギリスのイースト・アングリア地方にある海辺を臨む小さな街。夫を失って久しい、フローレンス・グリーンは新たな気持ちで動き出していた。
それは街の片隅にあるオールドハウスという、名前の通り古い民家を買い取って、昔からの夢だった本屋を始めること。
街には本屋はあったが、ちょうど廃業してしまい、ライバルはいなかった。そして、オールドハウスを持っていたオーナーとの弁護士を介した交渉も何とかなりそうな状況にあって、いよいよ本屋開業への道は開けたかのように思えた。
そんな最中、街の有力者から届いたパーティーへのお誘い。フローレンスは本屋開業のお祝いの言葉をもらえるものだと思い、参加することにする。しかし、そこで主催者のバイオレット・ガマート夫人からはとんでもないことを言われることに。。。
果たしてフローレンスは夫と共にかつて夢見た本屋を開業することはできるのだろうか。そして、ガマート夫人がフローレンスに言ったこととは。
イギリスの片田舎にある、海辺の街で本屋と自身の居場所を作るために、フローレンスの挑戦が始まる。
感想
ちょっとした前提
この本を読んだのは映画の後でした。そして、映画化されたからこそ、この本と出会うことができました。そのため、両作品とも好きです。そのことは最初に言わせてください。
そんな流れで原作を読んでいるので、どうしても映画のことを意識しながらの読書になりました。以下の感想は、その流れの上になりたっていることをご了承ください。
本の感想

『ザブックショップ』には閉鎖的なイギリスの片田舎が描かれています。町の人は粗野で、噂話好きで、昔からのルールやしきたりを重んじます。そこへフローレンス・グリーンはやってきました。
物語はフローレンスが海辺の街へ移住してから10年たったころから始まります。街の人とも普通に会話をしていますが、あまり馴染めていない様子は文章の端々から感じられます。
日本もイギリスも、そして昔も今も、美しく楽しそうに見える田舎暮らしというのは有形無形のルールがあり、それを知らないアウトサイダーには厳しいものなんだなと痛感せずにはいられません。
ただ、村の人たちもすべての人が敵対的というわけではありません。まぁ、そういった人ですら何かあれば手助けするし、お金を払えばその対価としての仕事はするといったもの。
それでも、フローレンスは過去の書店員としての経験と持ち前のガッツで本屋の開業にこじつけます。
銀行員や弁護士との地味な交渉を繰り返して、本の仕入れや店内の改装を少しずつ、淡々と物事を進めるフローレンスの姿ははとても忍耐強く、理知的な人に見えます。もしかしたら、そんな彼女を少し遠くに感じる人もいるかもしれません。
この辺の描写は長く仕事をしてきて、人生の晩年にようやく作家デビューしたペネロピ・フィッツジェラルドならではのリアリティあふれる描写がなされているような気がします。そのほかにもフローレンス自体はビジネスに敏感といいませんが、周りの人たちは業務に精通している様子が自然と伺えます。
そして、物語が進む中で特に生き生きと描かれているのが、開業当時の本屋の様子。何が本屋に並んでいるか、何が本屋にあるべきか、フローレンスのこだわりは興味深いものです。そして、そのこだわりは どれも当時の本屋を彷彿とさせるもののようです。さらに発生する予期せぬトラブルや望まない来客等も当時本屋なら経験したことでしょう。
しかし、そんな幸せな本屋の描写は長く続きません。物語が進むごとに不穏な動きが本屋の周囲で起こっていることを著者はにおわせます。身の回りには嫌がらせが横行し、落ち着いたかのように見えた住民からの好奇の視線が再び送られるようになりました。そして、地方議会の法案に関する文章が多くなってきます。

そこに抗うように反旗を翻す、この地方の良心であり、土地のかつての盟主。でも、その行動をとるにはあまりにも遅かった。そして挫折を経験するフローレンス。
夢見た彼女にとって、それはあまりに厳しい現実。誰もが手を差し伸べてくれることなく、ガマート夫人の策略にはまってしまった。それは彼女が未熟だったから、それともガマート夫人があまりにも狡猾で賢かったからなのか。
いずれにせよ彼女は2冊の本を携えて街を後にします。その後彼女がどうだったのか、そして街に残された彼女にかかわった人、そしてかかわらなかった人の未来はどうだったか、について本には描かれていません。
それは読者が想像するしかないのです。もしかしたら、その想像の余地が映画化につながった一つの要因なのかな、と思ったりもしました。
総じて感じられたのは、緻密でディテールに富んだ一つ一つの描写とは対照的に、様々なところに物語的な余白を感じさせ、それを読者に補わせるペネロピ・フィッツジェラルドの文章は、その世界に浸るのに十分なものでした。
映画と相まってということもあるかもしれませんが、楽しい時間を過ごさせていただきました。ちなみに『テムズ河の人々』読もうかな、と思ってサイトを調べたところアマゾンで24,980円。。思わず絶句してしまいました。
映画の感想

本当はこっちから書くべきなのかも。正直、映画を観るまではフィッツジェラルドのことは名前でしか聞いたことがありませんでした。
映画をみる大きなきっかけとなったのはビル・ナイが出演していたことと、映画の題材が本屋さんだったこと。この二つのうちどちらかが欠けていたら、本作と出会う確率はぐっと下がったかもしれません。
結果、私はこの二つを理由に恵比寿ガーデンシネマで観ることができました。後々確認したら、配給会社が映画館を吉祥寺でもって運営していたようなのでそっちで観ても良かったかもと思いました。
とにもかくにも恵比寿ガーデンシネマで観た本作、とても満足いくものでした。内容は基本的には小説に沿いながらも、いくつかの盛り上げポイントを明確に用意してくれます。
それは本屋が完成する瞬間だったり、ガマート夫人との対立だったり、関係者と心を通じ合わせる瞬間だったりと。よりドラマチックでそこには感動を覚えます。
その脚色は、監督のフィルター、もしくは解釈を通したものです。オリジナル小説のフローレンスや関係者に対する描写は限定的。だからこそ、今回の映画のように様々なシーンを取りこみ、未来へと続くような作品へと仕上げていくこともできるのかもしれません。
鑑賞後は少しセンチな気持ちになりつつも、楽しかったなという気持ちが心に残るそんな映画でした。
次のページでは、本と映画の違いに触れますのでご注意を。