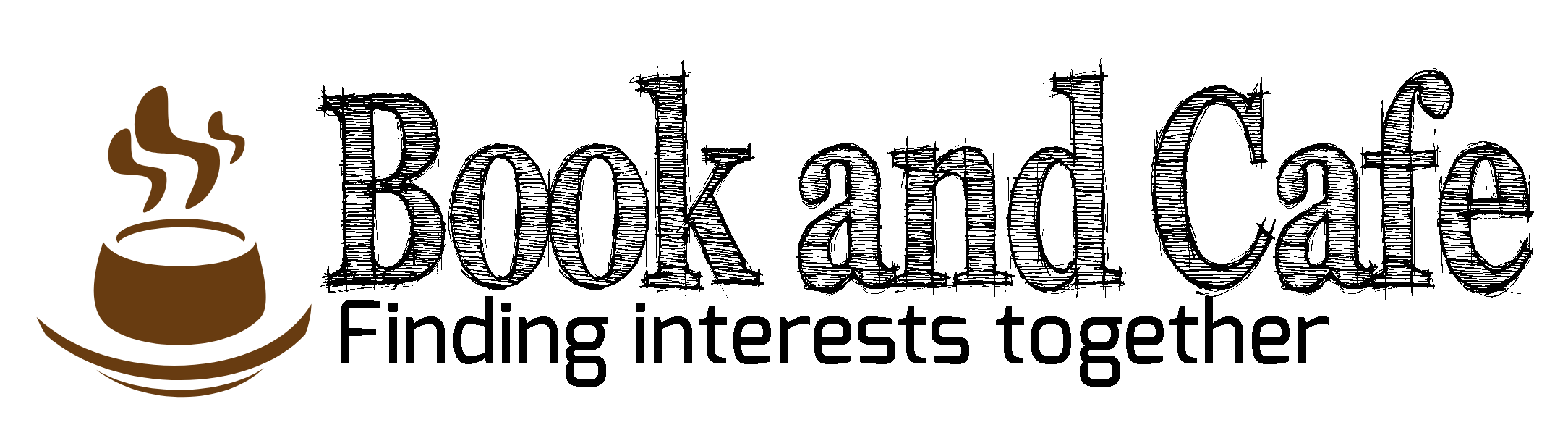【内容】
17世紀半ば、イギリスのオックスフォードでできたコーヒー・ハウス。市民社会の交流の場として活用されると、ロンドン、ケンブリッジなど、都市部を中心に広がり、1734年には551軒、最盛期となる19世紀初になるとロンドンだけで3000ものお店がで軒を連ねました。
なぜコーヒー・ハウスは当時のイギリス人に受け入れられたのか、当時の店内の雰囲気はどういったものだったのか、そしてどんな人に利用され、どんな会話がなされたのか、本書ではそれらについて様々な角度から切り込み、紹介しています。
そして、読者がおぼろげながらもコーヒー・ハウスの様子を想像できるようになったころ、そのコーヒー・ハウスから起こったジャーナリズムや文芸活動へと少し紹介対象を絞っていきます。そうすることによってよりリアリティのあるコーヒー・ハウスの日常を描いています。
最後にイギリス全体へと広がったコーヒー・ハウスがなぜ衰退していってしまったか様々な論があることに触れ、本書を締めくくっています。
この本はイギリスのコーヒー・ハウスがどういうものだったかのみならず、カフェが抱えている潜在的な可能性やタブーについて教えてくれる本でもありました。カフェ好きや歴史好きにはもちろん、カフェやコーヒーショップを運営する人たちにもお勧めしたい本です。

コーヒー・ハウス 18世紀ロンドン、都市の生活史 (講談社学術文庫)
小林章夫、講談社、2015-10-23
内容を振り返りながらの感想
第一章18世紀のイギリスの生活史
| 1554年 トルコ・コンスタンティノープルに世界初のコーヒー・ハウス開店 |
| 1600年 イギリスで東インド会社設立 |
| 1640年代 ピューリタン革命 |
| 1645年 イタリア・ベネチア初のコーヒー・ハウス開店 |
| 1650年 イギリス初のコーヒー・ハウスがオックスフォードに開店 |
| 1652年 ロンドン初のコーヒーハウスがパスカル・ロゼによって開店 |
| 1665-66年 ペストの流行、ロンドン大火 |
| 18世紀初 ロンドンに3000店舗のコーヒー・ショップが存在 |
冒頭、コーヒーの世界の普及について少しだけ触れます。といっても基本的にはいかにヨーロッパに入ってきたかのころから。フランシス・ベーコンが著書『森の森』でコーヒーのことに触れ、その味については評価していなかったものの心が落ち着く飲み物と評していたことを紹介。また、少し変わったところでは日本へ紹介する欧米人の心境についても紹介しています。特にシーボルトの本で日本人に対してコーヒーの売り込みが上手くいかなかったことに対する嘆いている部分を紹介しています。
その後、本書がテーマとするコーヒー・ハウスに話題は移っていきます。その際、官史サミュエル・ピープスとジョン・イーヴリンの日記を引用しながら紹介していくのですが、いずれも生活感ある文章で二人を介して当時を生きているようでした。
1650年にオックスフォードに初めてコーヒー・ハウスができ、学生の間で議論する場とつかわれたこと。1652年にロンドン、1670年代にケンブリッジに続々とでき、各々の場で多岐にわたる議論が交わされたことを紹介。ただ、コーヒー・ハウスが人気を博していく中で、大学近辺では生徒が授業を受けずにコーヒー・ハウスに入り浸るとか、コーヒー・ハウスが女人禁制だったことから夫人から多くの批判を受けた等、必ずしも各方面から歓迎されていなかったことについても触れます。
そんな批判にさらされながらも、コーヒー・ハウスの人気は衰えませんでした。この本ではその流行の原因について、17世紀末に発行された『コーヒー・ハウス点描』がタバーン(飲み屋)との比較したうえでの指摘と断ったうえで、(1)値段が安いこと(1ペニー程度で2-3時間店で過ごせる)、(2)酒がないのでまじめな話ができる、(3)交流を楽しめる、の3つを挙げています。その様子をペニー大学といわれることについてもふれつつ、やがて立地や利用者による差別化が始まります。
劇場の近くのものには劇団関係者や観劇者が、国会近くには政治家や官僚が、港湾近くのものには船主や船舶関係者が、といった具合に分かれていくことになります。そして、その客が固定化していくとともに、店の利用ルールも整備されていき、洗練されていく一方で、馴染みの客以外は入りにくい状況が生まれていきます。
さらにコーヒー・ハウスの発展する中で様々な逆風が吹きます。すでに上で紹介した通り、競合しているタバーンやレストラン等からの反対、また入店が許されない女性陣からの抗議。加えて、店内で政治に関する不平・不満が話されるのを嫌って王からの制限令の公布等。
そのうえ、世間的に起こったペスト病の流行とロンドン大火も起こります。それらについて本書でもデフォーの著作や当時の人々の日記を通して触れます。ペスト病の流行期は店内に入る際に咳している有無を確認したり、現代のようにレストランやコーヒー・ハウスの営業を制限したりと、厳しい局面だったようです。ただ、それでも、今と違って交流の場が限られていたこともあって、コーヒー・ハウスに人々が集うことをやめませんでした。また、ロンドン大火の後にも、すぐにコーヒー・ハウスが営業再開している記録があるとして、当時の人々のたくましさやコーヒー・ハウスに対する期待や先行きの明るさがあったんだろうと感じられました。
第二章ジャーナリズムの誕生
次の章はジャーナリズムについて。といっても、今でいう格式高い”ジャーナリズム”という意味ではなく、大衆の興味が様々な方向へ向かう中で日々の出来事を”記録して(journal)”、それを伝達するニーズが生まれ、冊子のような雑誌や新聞が広まっていく中で、コーヒー・ハウスもそれらを置くようになって、さらに客がそれらに掲載されている情報を知るために訪れるようになっていく様子が書かれていす。
結果として新聞や雑誌は読者層を飛躍的に広め、有名な『スペクテイター』や『タトラー』などの大衆紙が登場する流れを丁寧に描いていきます。『スペクテイター』や『タトラー』についてもその内容はSpectateからきていることが容易にわかるように、(世情の)観察をメインとしたものであって、その世間は政治や国内の出来事に関する情報あれば、隣近所のゴシップやコーヒー・ハウスでの出来事も含まれ、幅広い内容だったそう。そして、紙面の中には今まさに台頭してきている富裕層がいわゆる世間の常識や良識を形成していくことにも使われたようです。それがコーヒー・ハウスにおかれた新聞や雑誌を通して読者自ら意欲的に行われたというのは面白いところでした。
一方で、専門化していくコーヒー・ハウスならではの冊子(新聞)も現れます。有名なのは現在も世界最大規模の再保険会社であるロイズ。もともとはロイズ・コーヒー・ハウスに出入りする人々の情報を店主がまとめて『ロイズ・ニュース』として週3回発行していました。これを顧客に渡したことがきっかけとなって、この店は不動の地位を得るようになります。やがて、これらの系譜を受けついだ人々がロイズ保険会社を設立することとなります。他にも証券取引所のベースとなったコーヒー・ハウスもありますが、この本ではその他の経済に関連したコーヒー・ハウスの動向は語られていません。その点は残念でしたが、大衆、といっても富裕層ですが、彼らがどういうことを知りたいと望み、知識を得ていったかをしることのできる章でした。
第三章 ウィットの世界

投函箱として使われたライオンヘッドのイメージ図
3章では17~18世紀のコーヒー・ハウス中心の文壇の世界について紹介しています。当時の貴族社会に受けの良かった詩人であり、劇作家でもあったジョン・ドライデンはウィル・コーヒー・ハウスを利用し、そこに仲間を集め、またそこで訪問者と議論を交わすことによって当時の文壇の流行を築いていきます。そりが合うものもいれば、合わないものもいたそうで、『ガリバー旅行記』などで知られるスウィフトはそりが合わなかった代表格で、当時のコーヒー・ハウスを訪れた際の出来事を批判的に書いている文章が紹介されています。
ただ、ドライデンを中心とした仲間に認められると一躍文壇サークルの仲間入りするのは事実で、またそこの議論で作品は大いに洗練されたともしています。
一方で、世相や庶民に目を向けた代表格として『スペクテイター』の創業者の一人であるジョゼフ・アディソンを挙げています。そして彼がよく利用したのが彼の使用人を一時期していたダニエル・バトン(ボタン)が経営するバトンズ(ボタンズ)・コーヒー・ハウスです。彼は朝仕事した後に、このコーヒー・ハウスを訪れ、5,6時間過ごしたそう。
そして、このコーヒー・ハウスに設置したのがライオンの頭をした投書箱です。ここに投函された情報をベースに様々な記事が書かれ、紙面をにぎやかにし、読者にも大いに受けたとしています。そして、このような雑誌へ投稿したりすることで知名度を獲得するようになる作家も出てくるようになります。その辺の時代の移り変わりの表現は、これまた読みごたえがありました。
最後にコーヒー・ハウスの衰退について以下のことが原因でないかとしています。
(1)過剰出店ー18世紀初めにはロンドンだけで3000軒(当時の人口は約100万)あり、過当競争状態だったこと
(2)酒類提供等による治安悪化ー当初、コーヒー・ハウスでは酒類提供をしていなかったが、徐々に緩和されるとともに、賭博もなされるようになり、店内の治安・イメージが悪化
(3)交流の喪失ー上述したように固定客が進み、新規顧客が入りにくくなった
(4)各界からの反対ーチャールズ2世によるコーヒー・ハウス閉鎖令、女性からの反対請願、競合する酒場からの敵視等があり、いずれも乗り越えてはいるものの、常に良く思わない層がいた
(5)政府の植民地政策変更ー中東のモカコーヒーより安価なオランダの植民地であるジャワコーヒーがヨーロッパにもたらされ、イギリスの輸入は茶へとシフトしていった
(6)個人宅の良質化ーロンドン大火を契機にレンガや石造りの家が主流となると、自宅で過ごす時間が増え、パーティーを催すようになった
どれがメインと言い切ってはいませんが、これらが複合的に重なった結果、コーヒー・ハウスは徐々に姿を消していったと指摘し、本書を終えていました。
全体を通して
コーヒーだけに興味をもって、この本を買ったとしたら、失望してしまうかもしれません。しかし、コーヒーを提供する空間が17世紀~18世紀のイギリス社会に大きな影響を与え、そして人々の生活の一部になっていた様子がよくわかる本で、それは多くの可能性を示唆してくれるものでした。
本書内でも書かれていましたが、コーヒー・ハウスを利用するのは台頭しつつあるブルジョワジーが中心だったことに留意する必要はありますが、初期のコーヒー・ハウスのドアを開けば、そこには誰かしらがいて、店内をぐるっと見回して自分がなじみとする友人たちが座っている場所へ行き、そこで世情について話す。そして数時間過ごしたのち、満足してインやタバーンへと移って食事をする。コーヒー・ハウスは斯様に多くの人にとって開かれた空間でした。この本を読めば、そんなシーンが容易に想像できるようになります。
その様子は店を運営する人だったら誰もが羨むような光景ではないでしょうか。ではどうやってその光景ができたのか、それはエキゾチックな中東で飲まれる飲料への関心だったり、台頭する中流階級の社交の場だったり、知的好奇心の集う場だったりと、多くの要因が挙げられます。そしてそれらのいずれもがこの本で丁寧に紹介・考察がなされています。
そのようなムーブメントを一つずつ理解していくことは、現代の社会で起こりうるムーブメントを考えるのにとても有用なことだと思えました。個人的には、子本で紹介されていたような活気のあるコーヒーハウスが近所にできたら、これ以上幸せなことはないな、なんて思ったりしてしまうほど、内容に感銘を受けました。
本の概要
- タイトル:コーヒー・ハウス
- 著者:小林 章夫
- 発行:株式会社講談社
- 印刷:株式会社KPS プロダクツ (旧豊国印刷株式会社)
- 製本:株式会社 国宝社
- 第1刷 :2022年3月15日(5刷 2023年3月10日)
- ISBN4-06-159451-6 C0122
- 備考:講談社学術文庫 1451
関係サイト
日本コーヒー文化学会:https://jcs-coffee.org/
小林章夫先生は惜しくも2019年8月にご逝去されています。小林先生を偲んだ講演が以前、日本コーヒー文化学会主催で行われていました。その時の公演は一時期Youtubeでも確認できたのですが、残念ながら現在は非公開となっています。
同講演ではフランス料理研究を専門にしつつ、カフェやコーヒー・ハウスにも精通している山内秀文先生が簡潔に本書『コーヒー・ハウス』についてまとめられていました。いくつか提言もされていましたが、非常に簡潔で面白い講演でした。山内先生も非常に似た分野を開拓されている方なので、興味ある方は山内先生の講演や活動もチェックしてみてください。
次の一冊
イギリスのコーヒー・ハウスとよく対比されるのがフランスのカフェだと思います。そのカフェに造詣が深い人といえば、上述した山内秀文先生です。今回は山内先生が翻訳したユンカースの『ALL ABOUT COFFEE コーヒーのすべて (角川ソフィア文庫)』をお勧めしたいと思いつつも、カフェに割かれているパートが必ずしもメインではないので、今回はより明確な対比になるであろう『パリとカフェの歴史』を紹介させてください。

ルタイユール,ジェラール,原書房,2018-02-22
この本はフランスではじめてカフェができた17世紀中ごろから18世紀までを本書と同様に様々な角度から紹介しています。今回紹介した『コーヒー・ハウス』とほぼ同時期の世相が書かれている本です。似ている部分もあれば異なる部分もあり、読み比べることで当時の空気感がよりよくわかるはずです。
雑な閑話休題
今回ご紹介した『コーヒー・ハウス』もそうなのですが、コーヒー・ハウスがどういう空間でコーヒーがどういう役割を果たしかについて書かれているものでした。

By William Harrison Ukers – All About Coffee, page 617, Link
一方で、1650年ごろというと、コーヒー焙煎には長い柄のついたフライパンを使っていたとされていますが、同時期にシリンダー型のロースターがカイロ近辺で初めてできたころでもあります。

By This file was contributed to Wikimedia Commons by Conner Prairie as part of a cooperation project. The donation was facilitated by the Digital Public Library of America, via its partner Indiana Memory.
Record in source catalog
DPLA identifier: ab92df8478ed695bac532e581df00ba5
Conner Prairie identifier: http://indianamemory.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/CPTCPR/id/91 , Public Domain, Link
この焙煎機はすぐに人気となりヨーロッパで普及したといわれているので、こういうのもコーヒー・ハウスの普及に役立ったのかなと思ったりするわけです。
また、コーヒー好きだったら、同時どのようなコーヒーが飲まれていたのかも気になるところだと思います。コーヒー・ハウスの普及期だった17世紀中頃は中東のモカからの輸出品が多かったとされますが、そのころのコーヒーはいったいどんな生豆で、どんな状態で持ち込まれていたのか等々。
残念ながら、この分野における本はまだまだ少ないような気がします。もちろん、当時のことを記録した資料も少ないのかもしれませんが、そういう本があったら読んでみたいと思うばかりです。
良い本に出会うと芋づる式に知りたいことが増えますが、この本はまさにそんな印象を受けた本でした。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。また次の記事でお会いできることを楽しみにしています。