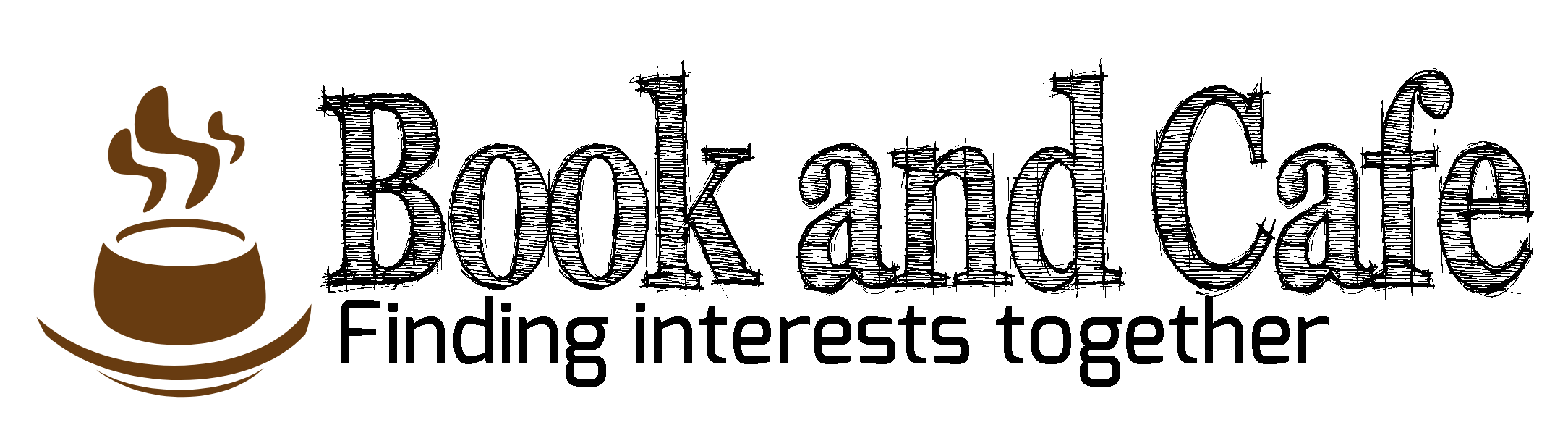内容
1993年、当時21歳だったこの本の著者である田中美穂さんはひょんなことから会社を辞めることとなった。彼女に残ったのは退職金を含め、約100万円。少し休職するでもなく、転職活動をするでもなく、彼女はやめることを決めた日にすでに不動産屋で店舗物件を探していた。そんな彼女が始めたのが古本屋。屋号は何とも独特な蟲文庫。ほとんど伝手もなく、書店員経験もない田中さん。古い四軒長屋の一部屋を借り、材木屋から木材を買い、棚づくりをした。ほとんどDIYなお店だった。本は親からもらったり、方々から集めたり。開業当初、本棚はすかすかだったとか。
そんな無計画とも思える古本屋が開店してから時を止めることなく25年がたった。この本では、そのうちの約20年について書かれています。それはまさに試行錯誤の連続。古本屋を始めたのに、駄菓子、アクセサリーを売り、とうとう趣味でやっていた苔まで販売したという・・・。お店ではそれだけにとどまらず、朗読会やライブまで様々なことが催された。でも、そんな時代を先どったお店はいまや地域を代表する本屋にまでなった。そんな風変わりな蟲文庫が倉敷という土地でどういう活動をしてきたか、そしてどういうお客さんに出会ってきたか、そんなことが本書にまとめられているんです
この本は決して古本屋さんの経営指南書ではないし、田中さん自身のアンテナがユニークすぎて、もしかしたら古本屋をするのに全く参考にならないかもしれません。でも、古本屋にしろ、雑貨屋さんにしろ、飲食店にせよ、何かをやろうとしているなら、色んなヒントがみつかるんじゃないかと思います。こんな自由なお店があってもいいんだと。何より田中さんと蟲文庫の魅力、そして古本屋さん稼業の可能性が心底伝わる一冊だと思います。

わたしの小さな古本屋 (ちくま文庫)田中 美穂筑摩書房2016-09-08
感想

本書は田中さんが会社を辞める1993年前後から2012-6年に至るまでの物語を一冊の本にしたものです(12年が単行本の出版年、そして16年に文庫化された年。いくつかのエッセイが本書の文庫化に際して追加されているのでこのような書き方にしました)。
巻末の解説と初出一覧によれば、本書の半分は『早稲田古本村通信』に寄稿されたものを加筆したもので、残りの半分は本書向けに書き下ろしたもの(ただし、すでにどこかしらの媒体で発表はされているとのこと)。そのため長い年月かけて記事がまとめられているわけですが、それが結果として良い味となっています。
そんな時間経過も含めて楽しめた本でしたが、個人的に読み入った点を以下に挙げてみました。私のテンションが伝わるといいな、なんて思います。
古本屋を取り巻く様々な魅力的な人たち

一番最初に掲載されているエッセイは2006年6月のもの。田中さんが会社を辞め、古本屋営業のために奮闘するところからはじまります。その様子は本当に大丈夫か?という向こう見ずなもの。そんなたどたどしい古本屋さんがいつの間にか押しも押されぬ中国地方を代表する古本屋さんになっていくのをこの一冊で追うことができました。
開店当初、お店の経営は相当厳しかったらしく、様々なアルバイトをされていたそう。時期によっては古本屋がメインなのか、アルバイトがメインなのかわからないときも。中でも郵便局での仕分けについては詳しく書かれれていました。その様子をみるに、今も昔もこの稼業は生半可な気持ちで手を出せるもんじゃないなと思ってしまいます。
この本ではそういうリアルな苦労話もありますが、どうしてもキラキラしたところに目が行ってしまうんですよね。中でも古本屋ならではの人との交流は羨望のまなざしを抱きながら読んでしまいました(まぁ、こういうのを読むといつか自分もと思っちゃうんですよね~)。
そんな出会いをいくつか。
田中さんは会社を辞めると倉敷駅前にある「ふるほんや読楽館」の店主森川さんに相談し、一冊の本を進められることに。それが志多三郎著『街の古本屋入門(光文社文庫。下リンクは97年に再発行されたものです)』。

街の古本屋入門―売るとき、買うとき、開業するときの必読書志多 三郎KG情報出版1997-08T
正直、この本はここで紹介されるまで知らなかったのですが、当時の古本屋開業バイブルとのこと。今でいうと荻窪にあるTitleの辻山良雄さんや本屋B&Bの内沼晋太郎さんが書いた本みたいなところがあるんでしょうか。あっ、いずれも新刊書店の開業に関するものだから、ちがうか。

本屋、はじめました 増補版 ──新刊書店Titleの冒険 (ちくま文庫)辻山良雄筑摩書房2020-05-29

これからの本屋読本内沼 晋太郎NHK出版2018-05-26
いずれにせよ、本の中で森川さんが指摘されているように立地や時代背景等を十分に考慮しながら読まないといけないわけですが、それでも未経験者にとってはバイブル的な本でしょう。
このアドバイスに代表されるように森川さんはことあるごとにアドバイスを送っていたようです。そんな彼女の森川さんの関係はとても素敵にうつりました。最初は古本屋の先輩後輩の関係(森川さんはさながら田中さんのメンター的存在だったんでしょう)から、共に戦う同志のような関係へ。たまにでてくるやり取りは(良い意味で)いつまでも大学生みたいな若さが感じられます。田中さんは森川さんとの出会いについて後に明かすのですが、なんと小学生のころからの付き合いだったとのこと。一度持った縁がいかに大事なのかを教えてくれているような気もします。
その後はお店をひいきにしてくれるお客さんが何人か紹介されます。本に登場するだけあって、その一人一人のエピソードがユニークなこと。盆と暮れにやってくる名前も知らないお客さんとの細々とした交流に双方の気遣いとやさしさを感じられたり、夜分に訪れ、しばしば閉店まで本を選ぶ職人気質のお客さんに一期一会の交流に胸を打たれました。本にはこういう宝石のような出会いがいくつも出てきます。
この辺だけでもNHKの朝の連続小説とか連ドラにならないかとになるんじゃないかと思わせるエピソードばかり。観てみたくないですか?個性的な店主を主人公としたローカル書店のドラマ。うーん、誰か撮ってくれないからしら。
そんな田中さんとともに蟲文庫は成長していくことに。
独自の進化を遂げる蟲文庫

開業当時は棚がまだ不十分なものだったと田中さんは振り返っています。開業資金も少なく、書籍商協会にも入る余裕もなく、結果として本の仕入れも満足にできてなかったのが理由です。
それでも日々近隣住民の古書を買い取り、棚が充実していったといいます。持ち込まれるものはなるべく買い取るため、中には専門知識の疎い古書もあり、幾分か勉強料を支払うこともあったそう(この辺は楽しそうですよね)。持ち込まれた本を棚を充実させていった田中さんですが、不思議と自身が好む棚が出来上がっていったといいます。文学、社会、思想、自然や写真といった多岐にわたる、でもどこかその人を物語るような棚ができていく。本屋はメディアとはよく言ったもので、時に世相を、時に店主自身を発信する場になりえるんだと思わせるエピソードかなと思えます。
そしてこの本、というか蟲文庫と切り離せないのが、田中さんの趣味でしょう。それは苔との縁です。田中さんは山登りやどこかに行った際には身を屈めて、苔の観察を趣味にしていたそう。田中さんが苔について語る章がいくつかありますが、古本屋について語るのと同等かそれ以上の熱量がありました(笑)。時には古本屋の時にはあまり感じられない、わがままさを感じられるくらい(その辺は以前読んだ「そと歩きノート」に通じるものがあったかも)。
やがて虫文庫では苔の販売をするようになります。そんな風変わりな蟲文庫にはそれを目当てにお客さんも集まってくるようになり、それが話題を呼び、メディアにも登場するようになります。蟲文庫ではそれまでも様々な展示や販売をしてきたそうですが、この田中さんの趣味を生かした販売は他の店と決定的に違う蟲文庫を印象付けるものになったんじゃないでしょうか。そして、そんな唯一無二の蟲文庫にお客さんも通うんでしょう。
私設公民館のような古書店「蟲文庫」

多くのことが蟲文庫というスペースで行われました。そして田中さんご本人は多数のエッセイも執筆するかた。そうすると儲かっているんでしょう?と思われるという。でも、ご本人曰く、状況は全く違うと。いまでは二足の草鞋状態ではなくなったものの、それでも全く儲からない稼業だと。そんな田中さん曰く、蟲文庫は「意地で維持」しているといいます。
蟲文庫では田中さんの人柄や知名度がゆえに多くのイベントが開催されるようになりました。本来は倉敷という土地では開催されないようなものも。だからこそ、田中さんは蟲文庫という場所を維持するんです。そこは人をつなぎ、地域の絆を紡ぐことができる場所だから。
ある日、「カタツムリ社」の故加藤哲夫さんがご自身の自然食品会社のことについて、「私設公民館だったんですよ」と表現されたという。そのことに田中さんは大いに納得したという。蟲文庫も倉敷で果たしていた役割は多くの人の拠り所であり、地域の交流の場である公民館のそれと同じだったんでしょう。もちろん限られたスペース故にできないことも多いでしょうけど、お店があることで救われた人も多いんだろうなと、文章の端々からわかりました。
たぶん、店を始める多くの人がそういう居場所になりたいと思って始めるのではないでしょうか。というか、そういう想いで始めてほしいなと思うわけですが。
もし、仮に自分がなにかを作ることがあったらそういう店を目指したい、そう思える本でした。
PS 早川さんの解説はいい味出していました。最近、岡倉覚三の『茶の本』を読んだからかもしれませんが、それに通じるところがあるような内容。気になる方は本文も解説をぜひ読んでみてください。
本の概要
- タイトル:わたしの小さな古本屋
- 著者:田中美穂
- 発行:株式会社 筑摩書房(ちくま文庫)
- 印刷・製本:中央精版印刷株式会社
- 装幀:安野光雅
- 解説:早川義夫
- 第1刷 :2016年9月10日
- ISBN978-4-480-43381-7 C0195
- 備考:本書は洋泉社より2012年2月に刊行されたものを増補加筆して文庫したもの。半数が「早稲田古本村通信」に掲載されたもの。その他本書のために書き下ろしたもの多数(Page222初出一覧参照)。Page148 自身→自信(誤字かな)?
関係サイト
- 蟲文庫HP:https://mushi-bunko.com/
- 店主 田中美穂さん twitter:https://twitter.com/mushi_b
- 本書で紹介された岡山文庫:https://www.n-bun.com/
蟲文庫のサイトにはかつての田中さんが書かれていた日記へのリンクもあります。また、オンラインショップもありますのでどんな本を販売されているんだろうと思った方はご覧になってみるといいかもしれません。個人的には倉敷の風景とともに綴られている日記の空気感がとても好きでした。
次の一冊
本書の後半で紹介されている早川義夫さんの『ぼくは本屋のおじさん』は本書の対になる本だと勝手に思っています。二人とも見様見真似で自分の居場所を作るべく始めた稼業。方や新刊本屋、方や古本屋。本が紡ぐ縁は違いますし、また自身のオリジナリティが異なるから経営方法だって全く違う。それでも本への愛情の注ぎ方やお客さんとの接し方はどこか通じるところがあるのかな、なんて。知らない人にはぜひ読み比べてほしいし、知っている人はもう一度この本のページをめくってみるのもいいのではないかな、なんて思ったりします。

ぼくは本屋のおやじさん (ちくま文庫)早川 義夫筑摩書房2013-12-10
ちなみに以前の読書記録を発見しましたのでリンクを(今も昔も相変わらず要領を得ない文章を書いているなとあきれています)。

当サイト【Book and Cafe】では次の一冊に関する短い紹介文を募集しています。気になったかたはSNSや下のコメント欄もしくはお問い合わせ にご連絡頂けますと幸いです。
雑な閑話休題(雑感)
本屋さんの棚は誰がつくりだすのか?
新刊の本屋さんも古書店も棚は誰が作るんだろうと思うときがあります。もちろん、店主さんなのですが、それでもTitleの辻山さんも今回読んだ蟲文庫の田中さんもそれはお客さんではないかと書かれています。
店主の嗜好した本が最初にありきで、それからどんどん派生していく。もちろん、店主のはずせないものや曲げられない信念はありますが、それと相反しない中で棚にも自我や自立心のようなものがめばえてくるのかな、なんて思ったりします。
今回紹介された古本屋さんなんてまさにそんな感じなのかなと思いました。特に田中さんは古書組合には属さず、お客さんからの仕入れが基本になっているのが個性的ですよね。もちろん、店の棚に著しくそぐわないものは仲間に流したりもされているようですが、、それでもそうなるといよいよ棚は地域住民の結晶のようなものなのかなと思ったりします。
少しいわゆる町の本屋とは違うのですが、ブックオフもそういうかんじが一部ありますよね。もちろん、ブックオフには独自の配本・陳列があるのでしょうけど、それでも五反田と新宿と荻窪のラインナップはだいぶ違う印象を受けました。あそこは購買層を意識しているのか、それとも単純に売主が持ってきたものを陳列していたのか。そういう想像もまだまだおもしろいなと思うばかり。
まぁ、そんなことを思いながら、今日も本屋さん巡りをしたいとおもいます。
今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。